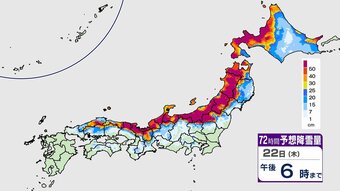消防署の隊員はふだん、管轄する市や町の中で活動をしています。
しかし大規模な災害が起き、現地の消防機関では対処できないとき、都道府県の枠を越えて救助活動をする応援部隊が、「緊急消防援助隊」です。

阪神淡路大震災をきっかけに作られ、山口県では2011年の東日本大震災や2020年の熊本県を中心とした豪雨災害などこれまでに6回出動しています。
大規模な災害時、連携して救助活動が行えるように、県内の消防を対象にした緊急消防援助隊の合同訓練がありました。

訓練は県内12の消防本部から、およそ100人が参加しました。
土砂災害が発生し生き埋めになった2人を助け出す想定です。まずは救助隊員が手で土砂を掘り、救出作業にあたります。
人がどのような状態で埋まっているのか、意識はあるのかなど、隊員同士でこまめに声を掛け合うことがポイントだそうです。1人目の救出が終わると、効率的に作業をするため、建設機械を使って大きな穴を掘り、ベルトコンベアで土砂を流しました。

役割ごとに連携を図ることで効果的な活動でき、2人の救出活動は40分ほどで終わりました。
岩国地区消防組合 中川冠消防士長
「日頃、県の消防本部が集まって共同して訓練するということがなかなかできないのできょうは連携など確認できて有意義な訓練だったと思います」
緊急消防援助隊は今後、地域ブロックや全国での合同訓練も行われる予定で、災害時の迅速で効果的な救助活動に備えることにしています。