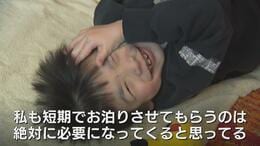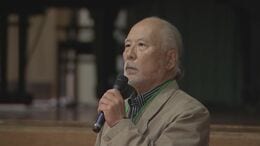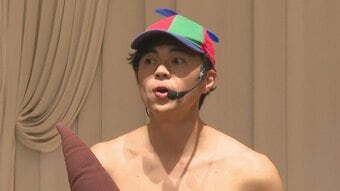■実現性60%と40%に込めた期待と現実味
鉄道解説系ユーチューバー 鐵坊主さん
「道路上に(ロープウエーを)作るとなると、ある程度の広い道路があるのが前提条件。新港地区みたいに、それなりに道路が広ければいいが。この辺りに来ると市街地なんで、なかなか…。市街地だからこそ、ここを通すことの意味はあるけど…」
ロープウエーの支柱は、石狩市の想定では道路の中央分離帯に建てます。
もし、道路に中央分離帯がない場合は、拡幅工事などの検討が必要になります。
ルートの道路の状況も見ながら、2人は最終地点、JR手稲駅にやってきました。
鉄道解説系ユーチューバー 鐵坊主さん
「麻生もそうだし、ここ(手稲)もそうだけど街中に入ってから(駅や支柱の)建設スペースをどう捻出するのか、なかなか大きな問題…。ここ(手稲)のほうが駅は作りやすい」

現場を見た2人、出した結論は?2人の見立てをこちらにまとめました。
【鐵坊主さん】
『実現性60%』
実現には『脱酸素時代の新インフラとして、いかにビジョンを示すか』が大切。
人口減少、人手不足の時代の新しい公共交通になるのでは、と話しています。
【おもしろ地理さん】
『実現性40%』
人口5万人規模の石狩市が導入する交通機関としては『ロープウエーしかない』としつつ実現性は40%。
課題は、道路での『既存の交通との兼ね合い』、混雑している道路への影響を抑えつつ整備できるかが、実現のカギになると話していました。
「ジッパー」の開発、6月から実験線での試験走行が始まる一方、今後、北海道特有の雪への対策も進めながら市としては10年をめどに実用化を目指しています。