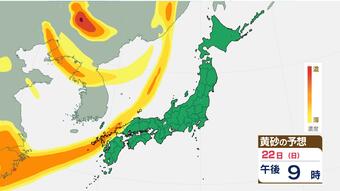小さい頃から「手のかからない子」だったA君。4歳半で自閉スペクトラム症(ASD)と診断された。IQは120。知的障がいを伴っていないため、小学校は「通常学級」への入学を選択した。しかし1年半後、A君は不登校となった。A君が不登校になるまでの過程を追いながら、診断のタイミングや学校・学級選びにおける課題を考える。

A君の母親「学級を選択する、誰かの一助になれば」
「静かすぎる子」の違和感
A君は幼い頃から「手がかからない子」だった。公共の場で騒ぐことはなく、おむつを替えている時には近くにあるベビーベッドの「使用法・注意事項」をじーっと見ているような子だった。

ただ、母親の心には小さな違和感があった。公園で他の子の輪の中に入らない。他の子が遊ぶ声を「うるさい」と言う。「…少し変わっているのかな?」―そう感じていた。
転機は3歳の時に訪れた。幼稚園の集団健康診断で、医師から「指示が通らないことがある」「足を引きずるような独特の動きをしている」との指摘を受け、障害福祉センターの受診を勧められた。
センターの予約を取り半年間の待機期間を経て受診。その結果、4歳半の時に自閉スペクトラム症との診断を受けた。
発達段階の確認(評価)をする長崎市障害福祉センター(もりまちハートセンター)。相談は完全予約制で、センターによると小児科の予約件数はここ数年右肩上がり。予約しても「半年待ち」の状態が続いているという。
「通常学級で大丈夫」
小学校入学を前にした発達障がいの診断。学校の選択はどうすべきなのか?両親は入学を前に、通学区域の小学校の教頭と面談した。A君は面談時とても落ち着いていて、教頭からは「通常学級で大丈夫だと思います。もし通常学級が難しいとなっても、通級指導教室には年度途中でも入れますから」との言葉をもらった。
通級指導教室とは、通常学級に在籍しながら週1~2回、個別・小集団で自立活動を行う教室だ。
「先生が言うなら、きっと大丈夫」。教頭の言葉に安心し、さらに後押しされて、両親は通常学級での入学を決断した。