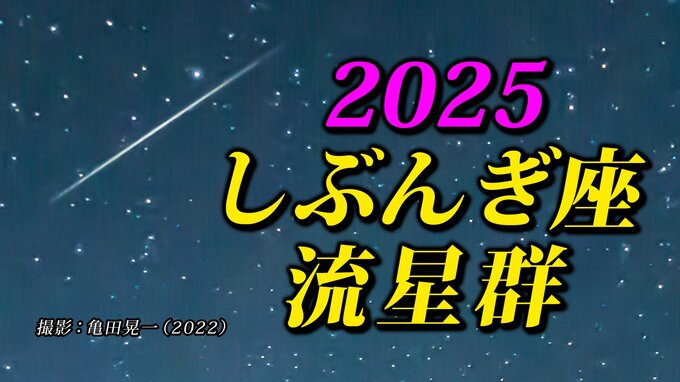しぶんぎ座流星群 について
『しぶんぎ座流星群』は三大流星群のひとつで、《極大期》には1時間あたり
30個と予想され、冬休みの時季で小中学生にもおススメの流星群です。
《流星出現期間》は12月28日(土)~1月12日(日)、最も多くの流星が
期待できる《極大期》は1月4日(土)午前5時頃と予想されています。
『しぶんぎ座』とは・・・
昔の人は、それぞれ星をつなげて星座を考えました。しかし長い年月が経つと、同じ星が異なる星座に含まれたり、星座の数が多くなり過ぎてしまいました。
そこで、1920年代に国際天文学連合(IAU)は「88の星座」を選定し、その際「しぶんぎ座(四分儀座)」は残念ながら外れ、現代では存在しない星座となっています。
星座としての「しぶんぎ座」はなくなりましたが、「しぶんぎ座」があった方向に放射点があることから、今でも「しぶんぎ座流星群」と呼ばれています。
その放射点は、現在の星座でいうと「うしかい座」と「りゅう座」の境界あたりです。なお「しぶんぎ座」は18世紀にフランスの天文学者が作りました。
注意)壁面四分儀座(へきめんしぶんぎ座)と呼ばれることもあります。
『しぶんぎ(四分儀)』って何?

「四分儀」は星の高さを測る観測機器です。「象限儀(しょうげんぎ)」とも呼ばれ、『伊能忠敬(1745~1818)』も日本地図を作成するために使っていました。星の高さから、その土地の「緯度」を決めていたそうです。