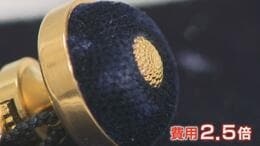10代で俳優デビュー、アイドル歌手としての経験ももつ斉藤由貴さん。現在放送中のドラマ『あのクズを殴ってやりたいんだ』で演じる主人公の母が特異な存在感を放っている。
スナックを経営して生計を立てている佐藤明美は、付き合う男はみんなクズという人生を歩み、孫ができる年頃になっても彼氏が途切れることがない。ややもするとだらしがないと思われがちなキャラクターだが、斉藤さんが演じるととてもかわいらしく憎めない人物となるから不思議だ。それは、斉藤さん自身に歳を重ねても色褪せない魅力があるからにほかならない。
時代を経て変わってきた考え方や、自身の価値観形成に影響を与えた人との出会いなど、長いキャリアを踏まえたうえでの“演者”としての心得を話してくれた。
“ベタであること”を受け入れるようになった

──スナックのママを演じての印象はいかがですか。
「明美」って、スナックのママとしてはこれ以上ないぐらいベタな名前ですよね(笑)。私、思うんですけど、ドラマにとって“ベタさ”ってとても重要なんじゃないかなって。キャリアを重ねていくにつれ、そのベタさを嫌ってはいけないんだなと感じるようになったんです。だから、役の名前が「明美」であること、そして、自分の娘に「ほこ美」「さや美」という名前をつけちゃうセンスがあるお母さんだということは役作りの一助になりました。
──“ベタであること”に抵抗を感じていたことがあるんですね。
私、18歳でデビューしましたけど、演劇や芸能に関わることはそのころから大好きだったんですよ。もともと、三島由紀夫の小説やルキノ・ヴィスコンティの映画を好むような中学時代を送っていたので、物語の世界に興味があったんです。でも、文学少女だったからか、分かりやすいものに対しては抵抗を感じる時期がありました。いまでも、わかりやすさを求めるがゆえにイージーになってしまうことへの危機感みたいなものは感じていて。ですから今回も、自分が物語のなかで担う分量を考えながら、「こういうスタンスを求められているんだろうな」ということを判断しながら演じることを大事にしたいと思っていました。
自分の年齢を的確に表現できる人でいたい

──演じていて特に楽しいシーンはありますか。
スナックで歌うシーンはとても楽しいです。いま、80〜90年代の曲が“シティポップ”といわれて、若い世代が興味をもってくれてるんですよね? 私はあまり詳しくはないんですが、そういうムーブメントが日本だけじゃなく世界にも広がっているとマネージャーから聞いたんです。私が明美さんとして歌っているのは、その時代その時代ですごくヒットした曲ばかり。それを歌えるのはとても楽しい経験でした。自分の曲を歌う機会も、いま風に言えば「ワンチャンあるかな?」と思っています(笑)。
──ママのチャーミングさは斉藤さんが演じられてこそだと思いますが、若々しさやかわいらしさを保つ秘訣を教えてください。
自分が緩むとお客さんにダイレクトに伝わってしまうんですね。俳優として気を抜かないように、まず正直に言うと、太らないように気をつけてはいます。年齢的にも体質的にもわりと太りやすいので、好きなごはんやアイスクリームを我慢することもあります(笑)。それと、明るい色の服を着ること。たとえば海外の女性って、年齢を重ねると赤やピンクの服を着るんですよね。もちろんやり過ぎて不自然になってしまうのもよくないので、さじ加減が難しいんですけど、「私はもう年だから派手なものは着れないわ」とは思わず、自分を上手に表現できる人でありたいなとは思っています。
──個人的に影響を受けた方はいらっしゃいますか。
昔、朝ドラ(1986年放送NHK連続テレビ小説『はね駒』)に出演したときに、私のお母さん役が樹木希林さんだったんです。ある日リハーサルのとき、希林さんがアンティークのジャケットを着ていらして。そのジャケットの背中に大きな丸いシミがあることにビックリして、「希林さん、そのジャケット、背中にシミがありますね」って言ったんです。そうしたら希林さんは「そうなのよ。だから買ったの。かわいいでしょ?」っておっしゃった。そのときすごくハッとして、「こういうところが素敵なんだ」と思ったんです。シミがあるからダメじゃなく、これがいいと思う自分を信じて堂々と着る。この出来事は、いまでも自分にとっての一つの指針になっています。希林さんにはこういう個性的なエピソードがたくさんあるからこそ、いまでも伝説になっているのかな。そこまでいったら勝ちだなって思うんですよ。