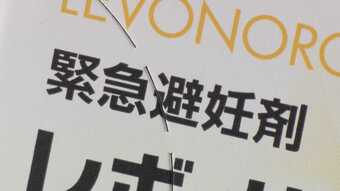◆新学期スタートは、子供たちの不安定さが増す

新学期が始まった今の時期は、子供たちの心も不安定です。9月から入院している男子中学生は、夏休み中に新型コロナに感染したため、学校に行くことができなくなったといいます。
堀川院長「その子は1学期から学校は行けなくなっていたので、本人の気持ちとしては『2学期になったら再スタートで頑張るぞ』という気持ちだったんだけれども(自宅)待機になって休まざるをえなくなって、行こうと思ったけど行けなかった。彼自身も、今すぐ死にたいと思っているわけではなくて、『死にたい、死にたい』とずっと続いていて、その裏には、『助けて』『不安でしょうがない』『寂しい』という気持ちだったり、『死にたいの裏にある思い』に、僕らも思いを馳せてあげることは大事なのかなと思います」
2006年に日本で施行された自殺対策基本法では、自殺を「社会問題」と捉え、国や自治体が対策を進めるように定めました。さらに2016年には改正法が施行され、自治体に自殺対策の計画作りが義務づけられました。福岡大学病院の衛藤医師は、「日本は若い世代に対する自殺予防の教育が遅れている」と指摘します。

福岡大学病院精神科 衞藤暢明医師「特に欧米では、若い世代で小学5年生とか6年生くらいからメンタルヘルスの問題について学んで、自傷したりメンタルヘルスの問題を抱えていると思った時は『必ず専門家に相談しましょう』という教育があるんですけど、(日本では)そのことを話題にしていいということは、教育として行われることがなかった」
◆アプリ窓口の相談員には大学生が
一方、福岡県は子供たちの自殺を防ぐため、今年から新たな取り組みを始めました。無料通信アプリの「LINE」を使った相談窓口の開設です。

RKB吉松真希「実際に相談窓口のアカウントにメッセージを送ってみます。中学生という設定でメッセージを送ると、大学生が相談員として返信してくれています。中高生にとっては年齢も近いので相談しやすいですね」
福岡県こころの健康づくり推進室 猪股祐子室長「若者は、対面の相談とか電話の相談というのがなかなか難しくて、通常からよく使っているSNSを活用した相談が効果的ではないかと」