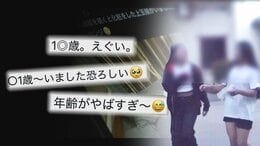移行期は「セカンドベストの選択肢」も
EVシフトや再エネ普及のためには、本来、多くの人々の意識改革・行動変容、産官での設備・インフラの長期投資、産学官連携によるテクノロジーの長期的進化が求められる。さらに各国の所得水準やエネルギー事情に応じて段階的にできることに取り組むことが望ましい。このため、「脱炭素社会の在るべき姿」へ一足飛びに瞬間移動することは難しい。
だからこそ、そこに辿り着くまでの道筋(パスウェイ)、すなわち「トランジション(移行)」段階の取り組みが重要となる。最終的な在るべき姿にこだわり過ぎると、トランジションでの現実的な取り組みの検討が不十分になりかねない。移行期では、EVや再エネの一択ではなく、「セカンドベストの選択肢」も備えて、国や企業がその時点でできる最大限の努力を尽くすことが重要だろう。
EVシフトの移行期には、燃費の悪いガソリン車から低燃費のガソリン車、さらにはHVやPHVへの段階的シフトが重要な取り組みとなる。再エネへの移行期でも、低効率の石炭火力からその高効率化、さらにはガス火力発電への転換を図ることで、脱炭素化に向けた貢献ができる。自動車のハイブリッドシステムや火力発電の高効率化技術では、日本企業が強みを持っており、途上国支援を含め国際社会への大きな貢献が期待される。
脱炭素社会の在るべき姿においても、EVや再エネの一択に賭けるのはリスクが大き過ぎるし、そもそもあり得ないのではないだろうか。モビリティ社会では、航続距離の多様なニーズやインフラ整備の進捗に応じて、パワートレインの多様な選択肢がやはり欠かせない。電源構成についても、再エネの一層の拡大に伴って、その安定化のためにバックアップ電源としての火力発電の維持更新投資の積み増し、系統用大型蓄電池の低コスト化の重要性が増す。一方で小型原子炉や核融合発電など新技術開発も必要だ。
脱炭素社会の最終的な在り方においても、多様な選択肢を備えるマルチパスウェイの考え方が欠かせないと筆者は考える。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 上席研究員 百嶋徹)