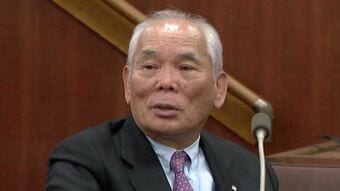「国外にいても欠席裁判ができる」
指針は台湾独立阻止を目的とした法律=「反国家分裂法」に基づく。処罰の対象になる行為として、台湾独立を目指す組織の設立、台湾の国際組織への加盟推進などを挙げているが、訴追の対象となる行為の範囲が明確ではない。
それらも驚きだが、「被告」と認定した人物が中国以外にいる場合であれ、いわゆる「欠席裁判」も可能としている点に注目したい。記者会見で、最高人民検察院(=最高検)の幹部がこのように答えている。
“「国家の安全を著しく危険にさらす犯罪に対し、裁判を行う必要があると判断した場合、最高人民検察院の承認を得たうえで、在外にいる被告人に公訴を開始することができる」
「国家分裂の罪の場合、最高刑は死刑。起訴期限は20年と定めている。ただ、国家分裂を目論む犯罪が特に悪質であれば、20年の訴追期限が満了したあとであっても、起訴することができる」”
「国外にいても欠席裁判ができる」「訴追期限の20年を過ぎても、裁判に持ち込める」――。つまり、中国が「台湾独立の動き」と認定したら、いつまでも、どこにいても、刑事被告人にする、ということだ。
一方、台湾の頼清徳総統はこの指針に対し「中国には台湾人の主張を罰する権利はない。越境して台湾人を訴追する権利もない」と反論している。実際、中国の司法当局は台湾に対する管轄権がないので、実効性はほとんどない。
中国の価値観の「幅の狭さ」が露呈
実効性がないのに、このような指針を示す中国側の狙いは、台湾への威嚇の一環なのだろう。習近平指導部は独立派と見なす頼清徳政権への圧力を強めている。今の中国の、コワモテ一辺倒、思考の硬直化を象徴する出来事だ。
冒頭に、日本で小さな町中華を経営しながら、台湾独立を主張していた亡命台湾人男性の話を紹介した。今日(こんにち)、台湾には民主社会が根付き、大多数の台湾住民が望んでいるのは「現状維持」=「台湾は事実上、中国と異なる社会が出来上がった」「今のまま、統一でも独立でもない」という考え方だ。亡命男性のような活動家はもう存在しない。
時代は大きく変わった。中国はその変化を認めず、自分たちの意に沿わない行為を、「台湾独立への動き」と認定し、裁判にかける決意だ。欠席裁判もあり、訴追も無期限。死刑だって可能だという。そんな振る舞いを、見つめる日本を含む周辺国、主要国の視線に、彼らは気付いているだろうか。
中国のいう「台湾独立への動き」は、中国自らの価値観の幅の狭さを裏返しているようにも思える。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。