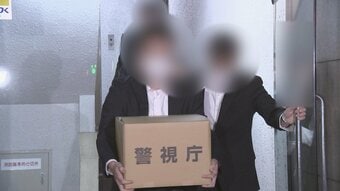先生の負担軽減策は? 公金納付システムの利用や地元大学との連携も一手
小川キャスター:
新しい取り組みですが、これこそ先ほど伊沢のおっしゃっていた「教師はこうあるべき」という“べき論”から、先生たちを解放できるような気もしますよね。
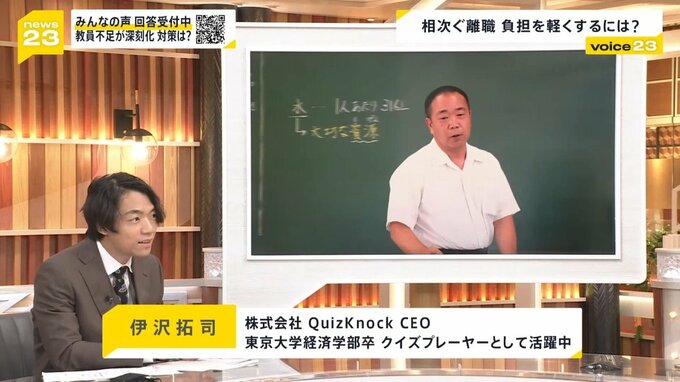
株式会社QuizKnock CEO 伊沢拓司さん:
やはり世の中の流れとして、良い学びや良いやり方はネットにあふれていたりします。先生は教えるティーチャーから教えに導くナビゲーター、良い学びにアクセスを繋ぐ存在になっていくべきかなと思っているので、そういうところに繋がってくる取り組みかなと思います。
僕も学校に毎月行って、生徒たちと喋るみたいなことをやっているのですが、先生方は笑い声を聞いたら「あ、誰々だな」「誰がふざけてるな」というのがわかるぐらいに、生徒への解像度が高いわけですよね。だから共有と一言でいっても、共有すべき内容がすごく多い。
もしくは、そこまでの解像度を求めないということも我々には必要かもしれませんが、その共有がちゃんと上手くいくことだったり、チームビルディングが上手くいかなかったり、先生の人気の差が出てしまったりすると、また新たな障害が生まれてきます。そういった課題を解決できるような環境を周りが整えていくこと、柔軟に求めていくことがすごく大事かなと思いますね。
小川キャスター:
体制のサポート態勢ということにもなりますが、いろんな工夫がまだまだできそうですよね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:
多くの先生は、使命感を持って働いているわけです。たとえば自治体に公金収納システムというのがありますが、先生が給食費を集めたりするのは、すごい雑用ですよね。そこは公金納付システムを使って、自治体がサポートできるわけですね。
それから、たとえば部活動は先生にとっても負担ですが、地元の大学生に助けてもらったり、補助してもらったりも十分ありうるわけです。そういう工夫をどんどんやっていく必要があるのと、やはり全体として国の助成というか、教育に対する支出をもっと増やしていくことが大事だと思いますね。
藤森キャスター:
現場レベルでは先生や学校がいろんな新しい取り組みをしていると思うので、保護者も皆さんも温かい目で、寛容な気持ちで見守りたいですよね。まずは、どんどんチャレンジしてほしいなと思います。