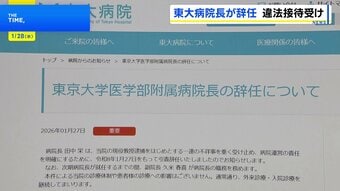5万か10万か…そこ揉めるところ?国民不在の「政治資金パーティー」の議論
94年の政治改革で政治家個人への企業・団体献金が禁止された。しかし実態は献金が「パーティー券」という形にかわり、企業・団体がパーティー券を政治家個人の政治団体から購入するという“抜け道”が残った。
今回、政治家が資金の集める方法としてパーティーを開くことに「納得できるか」という聞き方で調査を行った。結果は「納得できる」25%、「納得できない」73%。自民党支持層に限っても「納得できる」42%、「納得できない」57%と納得できない人が多数を占める。

しかし今回議論になったのは、パーティー券の公開基準を現在の20万円超から「10万円超」にするか「5万円超」にするか。はじめから「パーティーは存続ありき」で微に入り細に入る国民不在の議論ではなかったか。しかも実施は法律の施行後1年となる2027年1月1日から。自民党幹部の中からも「本当に世間が分かっていない」とため息が漏れた。
一方、野党側からも議論に水を差す出来事があった。立憲などは「パーティー禁止」の法案を提出したものの、議論の最中に立憲の岡田幹事長や大串選対委員長らがパーティーを実施しようとした(後に中止)。岡田幹事長は「法律ができるまでに自分たちの手を縛らなきゃいけないなんて話は普通はない」と強弁したが、本気度に疑問符がついた。
政策活動費「10年後公開」の不可解
とりわけ批判の矛先となったのは政策活動費の領収書公開が「10年後」となったことだ。また上限額が明記されなかったことや、10年後に領収書が出てきたとしても「黒塗り」にされる可能性があることが審議で明らかになった。さらに移行期間を経て実施するのは2026年1月1日からで、パーティー券の公開基準引き下げの実施時期とずれがある。この「10年後公開」には、共産党・小池書記局長がこう指摘した。

「政治資金収支報告書の保存期間は3年です。不記載などの罪に問われうる公訴時効は5年です。10年に一体どういう意味なのか、大体今の議論している政党幹部が10年後国会にいるのかどうかすらわからない全くふざけた中身だと言わなければなりません」
このほか、国会審議では「感熱紙タイプの領収書は10年後には印字が残らない」ということも議論になった。
これらの指摘に対し、岸田総理は「保存、提出、公開については、具体的な制度の詳細は早期に検討を行い結論を得るということになっている。具体的なこのルールについて、法案が成立した暁には、罰則の要否等も含めて、各党各派で会派で検討を行われるもの」と正面から答えることはなかった。
維新との間で合意した上限額含め、政策活動費の詳細について、総理は「検討」を連発し、“生煮え”感を印象づけるものとなった。
修正案の付則第14条には、「制度の具体的内容については早期に検討が加えられ、結論を得るものとする」との文言が書かれてあるが、元官僚で法案立案に携わった経験をもつ、ある野党議員は、「この表現は官僚の世界だと“やらなくて良いよ”ってことだから」と解説する。