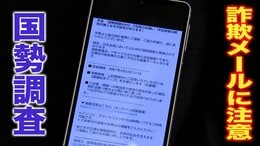店舗閉鎖に人員削減と、リストラ続々
そのツケは、結果的に傷を大きくし、ここに来て、リストラに次ぐリストラに追い込まれました。
北海道、東北、信越地方からは全面撤退。首都圏でもかつて全国一の売上げを誇った津田沼店を始め不採算店の整理を進め、店舗数は今年度、93店舗まで減少します。
従業員の早期退職募集も行い、本社も東京都心のセブン&アイ本社のビルから大森の店舗近くに移転するほどです。
当然のことながら、残る店舗も投資が滞りがちで、ヨーカ堂の店はどこか古臭く、リストラ続きの店頭からは活気が失われていくように見えます。
前向きな投資が行われず、リストラが終わったと思えば次のリストラが始まるという現実の一方で、「今後は、株式上場を目指して新たな成長を」などと言われても、現場には「絵空事」に聞こえるのではないでしょうか。
再建の道のりは、かなり厳しいものになりそうです。
「食」を中心としたグループを標榜するが
セブン&アイの井阪社長は、これまで「『食』を中心としたリテール(小売り)グループとして、スーパー事業は不可欠」だと説明してきました。
セブンイレブンの総菜も冷凍食品も、ヨーカ堂というスーパーの開発力、調達力があってこそ優位性が発揮できる。井阪社長は、スーパー事業の切り離しを迫る「モノ言う株主」たちに、そう反論して来ました。
それがなぜ、今、一定の資本関係は残すにしても、事実上の分離に大きく舵を切ったのか、井阪社長から明確な説明はありません。
スーパー事業再建のゴール、すなわち26年までの黒字化が見えて来たということなのか、それとも、資本効率を求める株主の圧力にもはや抗しきれなくなったのか。
もし最初から、「なし崩し的な分離」という終着点を見据えていたのであれば、ヨーカ堂の従業員や地域社会などに対しては、やや誠実さを欠いていると言わざるを得ません。
百貨店の西武そごう売却劇の、あの後味の悪さと、重なって見えてしまいます。
かつて「豊かな消費社会」の実現に向けて多角化を推進したセブン&アイは、グローバルなコンビニ事業に集中することになります。
日本最大の流通グループが、百貨店から撤退し、祖業のスーパーまで切り離すことは、時代の変化を感じさせるに、十分、大きな出来事です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)