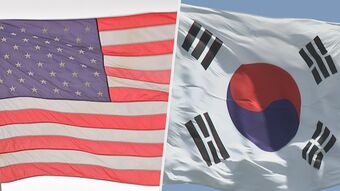“国宝級の発見”とも言われる巨大蛇行剣。私たちは1年間にわたって密着取材を続けて来ましたが、2024年3月、クリーニングが終了。その全容が明らかになりました。
巨大蛇行剣の保存処理に約1年密着 “謎の4世紀”に迫る数々の発見

「もう1枚ある、もう1枚。3枚目あった、3枚目」
2月、私たちの目の前で見つかったのは3枚の銅鏡。1600年前のものとみられ、こちらを向いているのが鏡の面だ。
調査補助員の大学院生
「映ってますよね…すごい」
ここは奈良市の富雄丸山古墳。2023年の年末から発掘調査が行われていたが、現場に建屋が設置されるなど、厳重な警備が敷かれていた。
2022年12月、ここで“国宝級の発見”とも言われる2つの極めて貴重な出土品が見つかっていたからだ。

1つは盾の形をした、これまでに前例のない特徴的な鏡「鼉龍文盾形(だりゅうもんたてがた)銅鏡」。

そして、もう1つが巨大な蛇行剣だ。曲がりくねった剣の全長は2メートル37センチ。あまりの長さに、当初は複数の剣がつながっているのではという見方もあったが、X線検査の結果、1本の剣だと確認された。

その巨大蛇行剣、3月、およそ1年間にわたるクリーニングが終了し、全容がついに明らかになった。

剣を握る柄(つか)の部分に備えられた雄大な装具。そして剣の先端、その先に驚きの発見があった。いずれも研究室での繊細なクリーニングによって明らかになったものだ。

この巨大蛇行剣は古代東アジアでも最大の鉄剣で、つくられたのは日本で国家の形成が進んだ、今から1600年前の「謎の4世紀」とみられている。前方後円墳が各地に築造されるなどしていたが、中国の書物などに記録が無く、分かっていないことが多い時代だ。
私たちは1年間にわたって巨大蛇行剣の保存処理に独占密着。「謎の4世紀」や、日本の刀剣の歴史に迫る、数々の発見を目撃した。