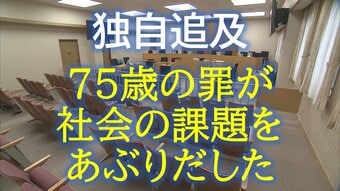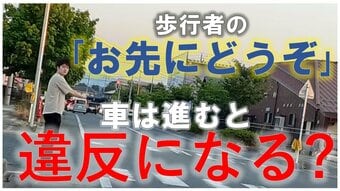続いては、みなさんと「お金」について考えていきます。
日銀は、おととい、「マイナス金利政策の解除」など、大規模な金融緩和策の見直しを決めました。2007年以来、およそ17年ぶりの利上げ。それが県内経済や、私たちの暮らしにどのような影響を及ぼすのか。見ていきたいと思います。
そもそも「マイナス金利政策」とは、経済活性化とデフレ脱却を目的に行っていました。具体的には、金融機関が日銀に預けるお金の一部にマイナス0.1%の金利をつける。そうすることで、預けたままだと支払う金額が増える。つまり、銀行に、企業への貸し出しや投資に充てるよう促し、経済を回そうという狙いがあります。今回、マイナス金利政策を解除したことについて、専門家の受け止めを聞きました。
山形大学・山口昌樹教授「金融政策自体としては分かりやすくなった。今後は標準的な金融政策に戻ることになる。賃上げが予想よりも大幅な上昇であることを確認できたので、このタイミングで政策変更を行ったのは適切だと考える」
国際金融を専門とする山形大学の山口昌樹教授は、今後の経済指標をチェックする必要があるとした上で、タイミングは妥当としています。
その背景にあるのが、大手企業を中心とした春闘での賃上げ。連合が15日に公表した平均賃上げ率は5.28%と、33年ぶりの高水準でした。さまざまなモノの価格が上昇していますが、日銀は賃金が物価を上回る状況が生まれている、つまり、マイナス金利政策をとらずとも経済が回っていくと予想しているわけなのです。
次に、暮らしの影響。
マイナス金利の解除で考えられるメリット・デメリットの一例をあげてみます。
メリットは、銀行などに預ける預金の金利が上がる。
デメリットは、住宅ローンの金利上昇などが考えられます。
山口教授は、暮らしへの影響をこう見ています。
山形大学・山口昌樹教授
「まだマイナス金利を解除しただけなので、家計に大きな影響があるわけではない。金利が上がってくるという話になれば影響は出てくる」
山口教授は、すぐに影響が出るわけではないとしながらも、もし金利が上がれば、住宅ローンの金利の支払いが増えて家計が苦しくなることも考えられるとしています。ただその一方で、アメリカとの金利の差が縮まり為替相場が円高方向に動けば、物価が下がるというメリットも期待できるとのことです。
では、県内経済についてはどうなのか。山口教授によると、企業は資金繰りのために金融機関から資金を借り入れることが多く、借りる時の金利が上昇すれば、大型の設備投資に慎重になったり、経営の悪化につながる懸念もあるということです。中小企業が多い県内は、攻めの経営をしにくくなることが考えられるということです。
県内経済も、暮らしについても「今後、金利がどうなるか?」そこが大事になります。今後の判断は。
山形大学・山口昌樹教授「ポイントは賃金の引上げ。中小企業や非正規労働者にまで波及してくるかどうかにある」
賃金の上昇 > 物価上昇になると、金利の引き上げに踏み切る可能性が高いということです。急速に利上げが進む事態は現状考えづらいが、個人で出来ることとしてあげられるのか・・・
・物価や賃金の動向を注視する。
・金利が上がる事態に備えて、事前に家計を見直しておく ことです。
物価、住宅ローン、株価など身近なところからお金について考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。