「安全性を担保していくということは、薬学部の使命」
粂教授にまず聞きました。「公立大学の現役の教授が、新型コロナワクチンを薬害の講義で取り上げて大丈夫なんですか」と聞きましたら「事実を学生に伝えることは問題ない」と。そして「安全性を担保していくということは、薬学部の使命であって、社会的にも重要だ」と、はっきりと言っておりました。
薬害の講義で取り上げられた事例は、どんなものなのか。例えば「サリドマイド薬害事件」についてはこのように書かれています。
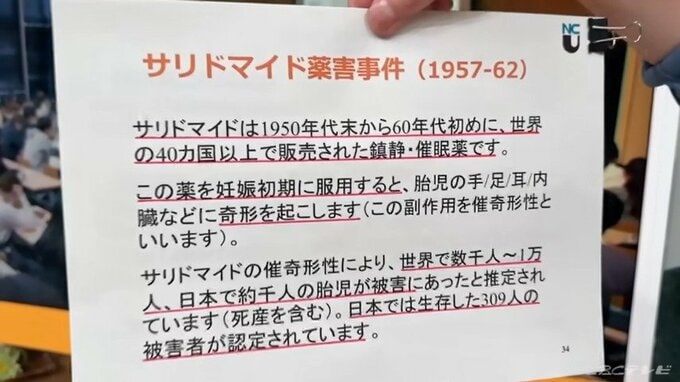
【サリドマイド薬害事件(1957~62年)】
サリドマイドは、1950年代末から60年代初めに世界の40か国以上で販売された鎮静・催眠薬。この薬を妊娠初期に服用すると、胎児の手・足・耳・内臓などに奇形を起こす。被害は世界で数千人~1万人、日本では約1000人の胎児が被害に遭ったと推定(死産も含む)されている。日本では生存した309人の被害者が認定されている。
こういった講義の中で実際に被害者をお呼びして、体験談を聞くという講義をやっていたわけです。そんな流れの中で、今回は新型コロナワクチンが取り上げられました。
資料には「新型コロナワクチンを考える ~ノーベル賞受賞技術の光と影~」。講演するのは、新型コロナワクチン後遺症患者の会の代表・木村さんと幹部の神谷さんです。

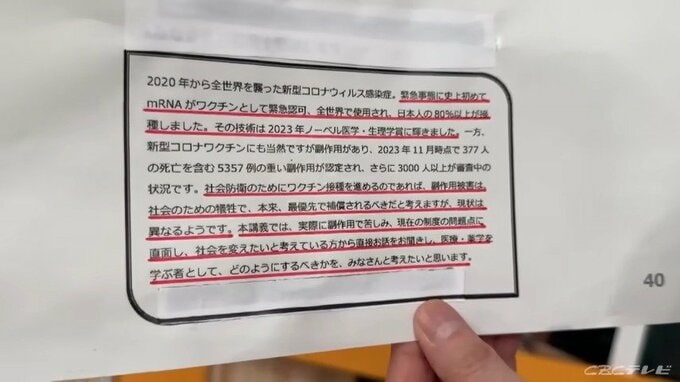
講演会の資料には、このように書かれています。
「緊急事態に史上初めてmRNAがワクチンとして緊急認可、全世界で使用され、日本人の80%以上が接種しました。その技術は、2023年ノーベル医学生理学賞に輝きました。
社会防衛のためにワクチン接種を進めるのであれば、副作用被害は、社会のための犠牲で、本来、最優先で補償されるべきだと考えますが、現状は異なるようです。本講義では、実際に副作用で苦しみ、現在の制度の問題点に直面し、社会を変えたいと考えている方から直接お話をお聞きし、医療・薬学を学ぶ者として、どのようにすべきかを、皆さんと考えたいと思います」
これが講義の趣旨ということなんです。実際に2024年1月23日に講義が行われ、取材しました。
開催された講堂には、約200人の学生が集いました。

空いている席は、ほとんどありませんでした。
将来、薬剤師を目指している方などが中心ということが言えると思います。そんな中で、患者の会の方が講演を行ったんです。


講演した患者の会の3人には共通点があり、3人ともワクチン後遺症の症状がまだ続いています。
3人共通してあるのは「ブレインフォグ」です。ブレインは「脳」フォグは「霧がかかったような状態」のことで、3人とも少し記憶障害のような症状が残ってるんです。そのため、お話していても途中で「あれ。私何の話をしてたんだっけ?」というような状況になるんです。この講演会中も複数回ありました。
また、このうちの1人は、胸の痛みがあり、杖がないと歩けないんです。この日も杖を持って、やってきました。足は講演中もずっと震えていて、不随意運動が今も続いていました。














