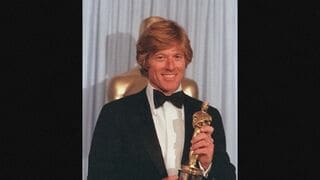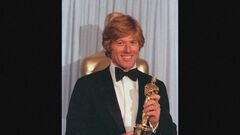(ブルームバーグ):在宅勤務を巡る議論が再燃している。恐らく今後何年も続くことだろう。この事実を認識しないと、個人のキャリアや経済状況、ひいては幸福度に悪影響が生じる可能性がある。
予想通り、トランプ米大統領はJPモルガン・チェースやアマゾン・ドット・コムに続き、連邦職員にフルタイムのオフィス勤務復帰を命じた。
これをきっかけに、対面での勤務を支持する人々と、新型コロナウイルス流行期以来在宅勤務やハイブリッド勤務を行ってきた人々との間の緊張が再び高まった。
そして、この対立がすぐに解決されることはないことを示すあらゆる兆候がある。
ビジネススクールINSEAD(インシアード)のマーク・モーテンセン准教授(組織行動学)は「現実問題として、この対立は解決不可能だ」と語った。
同氏は1990年代後半からリモートワークを研究しており、こうした働き方は非常に長い歴史を持っていると指摘する。
企業や国は、何世紀にもわたって「分散型ワーク」と呼ばれるものを活用してきた。ある研究では、1670年に設立されたハドソン湾会社が事実上「バーチャル」な組織であったことが指摘されている。「歴史上のあらゆる帝国は、リモート型の組織だった」という。
フレキシブルワークにはさまざまな側面があり、議論が尽きない。権力、生産性、仕事の意義といった問題が絡んでくる。世代間の違いにより、多くの人が考えるよりもずっと長い間、この議論は続くだろう。
「2025年はオフィス復帰の年になるかもしれない」と、求人サイト、インディードの人材戦略アドバイザー、カイル・M・K氏は言う。
同時に、企業は今まさに体制変化の真っただ中にあるとも述べた。
オフィス復帰を推進する年配のマネジャーたちも、間もなく退職を迎える。ミレニアル世代やジェネレーションZが管理職に昇進するにつれ、彼らは自身のキャリアの初期に慣れ親しんだ多くの柔軟性を復活させるだろうと、M・K氏は予想している。
専門家たちに話を聞いたところ、他の雇用主がオフィス出勤義務を課していると耳にして自分のことを心配している人への最大のアドバイスは、慌てないことだ。
人材紹介会社コーン・フェリーのプロフェッショナルサーチおよび臨時雇用担当の最高経営責任者(CEO)であるマイケル・ディステファノ氏は「大多数の人の立場は中間的だ」と言う。全員をオフィスに戻すことを大々的にアピールしたいと考えている例外的な雇用主もいるかもしれないが、その大半はノイズにすぎないと同氏は述べた。
最近の発表の中にも、多少の余裕があるように思えるものもある。この件に関する最新のホワイトハウスのメモを見ると、「できるだけ早く」という曖昧な期限が使われており、例外規定も設けられている。
また、リモートワークは長期的な問題であるため、現在の職務で不可能になっても、別の職務では可能になるかもしれない。
しかし、安心しきっていてもいけない。管理職を指導するモニーク・バルクール氏は、リモートワークを取り巻く環境の最新情報を常に把握しておくよう被雇用者に勧めている。
一部の企業では、退職を促す手段として、オフィスへの出社を義務付けるケースもある。このような企業では、リモート勤務の特権に固執するのは難しいとバルクール氏は指摘した。
また、一部の求職者は期待値をリセットする必要があるかもしれない。
ブティック型人材紹介会社ABSスタッフィング・ソリューションズのアリエル・シューアCEOはハイブリッドモデルを好んでいるが、求職者から「新しい仕事が欲しいが、同時に、日中エクササイズクラスに通い続けられるほどの柔軟性も維持したい」というような期待を聞くと、「驚く」ことがあると話す。
「仕事なのだと自覚すべきだ」とシューア氏は述べた。
原題:Experts Are Bracing for a Long Battle Over Remote Work: Wealth(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.