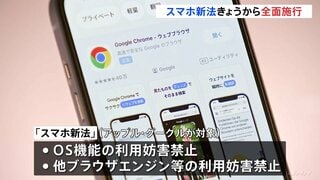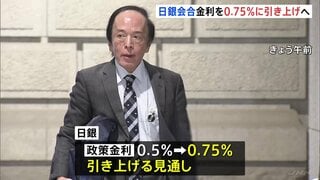(ブルームバーグ):9日の日本市場では株式が続落。米国の利下げペース減速やトランプ次期政権の関税政策に対する懸念が重しとなり、ハイテク株や自動車株を中心に売られた。
債券は上昇。長期金利が2011年5月以来の高水準を付けるなど売りが先行した後、30年利付国債入札の強い結果を受けて超長期債中心に買い優勢に転じた。円相場は1ドル=158円台前半から一時157円台後半まで反発。毎月勤労統計が予想を上回ったことや日本株安によるリスク回避の動きが円買いを促した。
T&Dアセットマネジメントの浪岡宏チーフ・ストラテジストは「米景気は良いが、金利が高い状況が続いていることは株式の重しになり、日本への波及もある」と述べた。
債券市場では高水準のインフレや政治的混乱、政府債務の膨張を巡る懸念から、世界的に国債利回りが重要な節目に向かって上昇している。8日には米国の20年債利回りが一時23年以来となる5%台に乗せ、英国の10年債利回りは08年以来の高水準を付けた。
国内でも新発30年債利回りが一時2.35%と10年以来、新発40年債利回りは2.705%と08年以来の高水準を付けた。入札を順調にこなしたことで30年債利回りはその後低下に転じたが、1月は超長期債の入札が3週連続で実施されるため、需給に対する根強い不安から戻りは限定的だった。
株式
日本株は続落。ハイテク企業や自動車のほか、海運や商社、保険などが安く、東証33業種のうち、その他製品などを除く30業種が下落した。
TOPIX下落に最も寄与したのがトヨタ自動車で2.2%の値下がり。指数構成銘柄2123のうち、1647銘柄が下落、上昇は409銘柄にとどまった。
T&Dアセットの浪岡氏は、投資家の懸念が強まる中、20日のトランプ次期大統領の就任式を前に同氏の関税計画が日本の輸出企業に与える影響への懸念も高まっていると指摘。「外需系、輸送機器を売ってサービス、小売り、食料品や医薬品など内需に逃げるトレンドが進んでいる」と話した。
キーエンスや日立製作所、東京エレクトロンが下げ、電気機器指数がTOPIXの下落寄与度トップ。主要顧客である中国の長鑫存儲技術(CXMT)が米政府の「中国軍事企業」リストに追加されたことを嫌気し、KOKUSAI ELECTRIC株も安い。
川崎汽船など海運株も下落。米港湾の労使協定暫定合意でストライキ突入によるコンテナ市況上昇への期待が剥落した。海運業指数は一時5.4%安と業種別で下落率トップとなった。
債券
債券相場は上昇。30年債利回りは10年以来の高水準の2.35%から入札後に低下に転じた。30年債入札では、投資家需要の強弱を反映する応札倍率が20年11月以来の高水準となった。
三井住友トラスト・アセットマネジメントの稲留克俊シニアストラテジストは「利回り水準がここまで上昇すると需要が喚起される。新発債だったことも大きい」とし、落札価格や応札倍率、テールとどれを見ても良い結果と指摘した。ただ、1月は超長期債の入札が続き、「米金利先高観もあるため、21日の40年債入札をこなせるめどが付かないと、金利の上昇や高止まりが続く可能性はある」と述べた。
入札結果によると、最低落札価格は99円90銭と、市場予想99円75銭を上回り、小さいと好調を示すテール(落札価格の最低と平均の差)は2銭と、22年2月以来の小ささ。応札倍率は3.72倍に上昇した。
新発国債利回り(午後3時時点)
為替
東京外国為替市場の円相場は一時1ドル=157円台後半に上昇。昨年11月の毎月勤労統計で基本給に相当する所定内給与が32年ぶりの高い伸びとなり、日本銀行の追加利上げの支援材料になるとの見方から買いが先行した。買い一巡後は10日に米雇用統計を控えて持ち高調整も入り、上げ幅を縮めた。
オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)外国為替・コモディティ営業部の町田広之ディレクターは、毎月勤労統計に反応して円が買われた後は、時間外取引での米長期金利の低下や「株式市場の軟調な展開が円買い・ドル売りにつながった」と指摘。「金利が上昇した日本国債を買う動きもあるのではないか」との見方を示した。
一方、ソニーフィナンシャルグループの森本淳太郎シニアアナリストは、今回の統計だけで日銀の利上げ期待が高まっていくのも難しいとし、米雇用統計の発表を控え「円ロングには傾けづらい」と述べた。
日銀がこの日開いた1月の支店長会議では、人手不足の下で25年度も賃上げの継続が必要との認識が広がっていることが多く報告された。大和証券の石月幸雄シニア為替ストラテジストは、地域経済報告(さくらリポート)も含め「全体的に見るとオントラックな内容」とする一方、中小企業の収益面の厳しさや人件費の価格転嫁の難しさなど「一部の表現に円売りで反応した面もある」と指摘した。
この記事は一部にブルームバーグ・オートメーションを利用しています。
--取材協力:横山桃花、日高正裕.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.