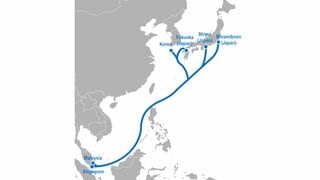(ブルームバーグ):米連邦準備制度は昨年9月半ば以降、計1ポイントの利下げを実施したが、米30年債利回りはほぼ同じ程度上昇。直感的には理解しにくい長短金利の乖離(かいり)が起きている。
だが、この状況は米国だけではない。英国でもイングランド銀行(中央銀行)が金融政策を緩和しているにもかかわらず、英30年債利回りが1998年以来の高水準に達した。
その理由は、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)によって引き起こされたインフレ圧力が世界経済に何年もくすぶると投資家が懸念しているためだ。加えて、パンデミックを受けたロックダウン(都市封鎖)中に巨額の資金を投じ、景気刺激策を講じた各国政府は依然として多額の債務を負っている。
年限が比較的長い債券の特徴は
富裕国が発行する国債は世界で最も安全な証券として広く認識されており、米国債はその最たるものだ。30年債などの超長期債を発行する国は多く、中には100年債で資金を集める国もある。これらの国債は長期投資家からの需要が多いが、一般的にボラティリティーも高くなる。

その理由は、インフレに敏感なためだ。インフレが加速すると債券から得られる金利の購買力が低下するため、債券は売られやすい。また、インフレによって30年債の金利の相対的価値が、年限が比較的短い債券よりも大きく損なわれることになる。
また、年限が比較的長い債券に関心を持つ投資家が限られているため、売買がそれほど容易でない側面もある。こうした債券を求めることが多いのが、債務返済を補うキャッシュフローの源泉となる固定金利資産が必要な保険会社や年金基金などの機関投資家だ。
値下がりペースは
純資産総額が約500億ドル(約7兆9000億円)の上場投資信託(ETF)「iシェアーズ 米国国債20年超ETF」(ティッカー:TLT)は、超長期の米国債にのみ焦点を絞ったETFとしては世界最大だ。
米国の利下げが始まった昨年9月中旬以降、同ETFは約15%値下がり。これはかなり大きい下落率だが、2020年の高値から23年10月までの52%安に比べればまだ下げ幅は小さい。
当時は過去最大の売り局面で、世界的なインフレ急上昇を受けた各国・地域中銀の利上げが背景だった。最近の債券安で興味深いのは、その値下がりのペースと、各中銀が金融緩和を進める中で起こっているという事実だ。
売り要因は
債券投資家は主要国でインフレ圧力が長引くことを懸念。長期債売りは昨年12月に加速した。
特に米国では経済統計の発表を踏まえインフレ率が米連邦準備制度が目標とする2%を上回る水準にとどまるのではとの懸念が浮上。米連邦公開市場委員会(FOMC)は25年に見込む利下げ回数を従来予想から減らした。
またトランプ次期大統領が検討している減税や輸入関税の影響で、強靱(きょうじん)さを示す景気にインフレ圧力が加わる可能性もある。これが、年限が長めの債券を保有する際に投資家が求める見返りとして知られるタームプレミアムを押し上げる一因となっている。
入札が要因か
その通りだ。パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)は昨年末、米財政赤字が膨らんでいることを考えると、償還までの期間が長い米国債を購入することには「消極的」との見方を示した。
債券利回りの上昇に対する入札の影響を評価する指標の一つは、いわゆるスワップスプレッド(同じ年限の国債利回りとスワップ金利の差)だ。
入札が市場の重しとなっている場合、買い手を引き付けるために債券利回りがスワップ金利よりも上昇することが期待される。米30年物スワップスプレッドは80ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)超と、年初の約70bpから拡大している。
長期債利回りの上昇余地は
過去を振り返ると長期債利回りには上昇余地があるかもしれないが、どこが上限かと明言することはできない。23年10月に30年債利回りが5%を超えた際には魅力的な利回り水準を求める債券買いが広がり、利回り上昇が一服。23年末の30年債利回りは約4%となった。
一部の債券投資家は利回りが再び急上昇する可能性を排除していない。INGは米10年債利回りが25年末までに5.5%近辺に達すると予想している。
また、ティー・ロウ・プライスは米国の財政悪化とトランプ氏の政策によるインフレ高止まりにより、10年債利回りが6%に達する可能性があるとみている。
米プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社アポロ・グローバル・マネジメントのチーフエコノミスト、トルステン・スロック氏は、米国債利回りが急ピッチで上昇しており、英国でトラス政権を退陣に追い込んだような債券市場の混乱が起こり得ると考えている。
原則的には、市場の動きが加速すれば中銀が介入する可能性がある。米連邦準備制度は12年、短期債を売却して長期債を購入する「ツイストオペ」を実施。また、22年にはイングランド銀が無秩序な売りに対応するため、長期債の購入を開始した。
米連邦準備制度もイングランド銀も今のところ、同様の措置を検討している兆候はない。
他の資産への影響は
理論上は債券利回りが上昇すればするほど、マネーマーケットファンド(MMF)や株式など他の資産クラスから資金が引き揚げられる。実際、より高い利回りを確保しようとする動きから、債券ファンドは昨年、記録的な資金流入となった。
実体経済への影響は
米国では住宅ローンの借入期間が一般的に30年となっており、年限が長めの債券の利回りは特に重要だ。
つまり、貸し手は債券市場での長期債利回りの水準を参考にして金利を設定し、リスクをヘッジすることが可能になる。
大企業も社債発行などの際には長期債利回りを参考にすることが多い。市場金利が上昇し続ければ、住宅購入や事業運営における資金調達コストが膨らみ、経済が減速する可能性がある。
原題:Why Long and Short Global Rates Fell Out of Step: QuickTake(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.