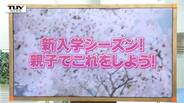23日、臨時国会が開会しました。
岸田総理は所信表明演説の中で、所得税の減税などを念頭に、経済対策に力を入れていくと強調。そして、社会が直面する課題について、こんな発言をしました。

岸田総理「地域交通の担い手不足や、移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応しつつ、ライドシェアの課題に取り組んでまいります」
演説の中で出てきた「ライドシェア」という言葉、ご存じでしょうか。
Rideが乗る、Shareが共有、いわゆる、相乗りという意味の単語で一般のドライバーが自家用車を運転し有料で乗客を運ぶサービスをさします。
ライドシェアは、アメリカでは2010年頃から普及し始め、生活の足となっています。
総理は、このサービスの解禁を検討していくと表明したわけですが、その背景には、少子化やコロナ禍などによるタクシーやバスといった地域交通の担い手不足があります。
解禁することでどんなことが考えられるのか、県内のタクシー事業者の受け止めを聞きました。
県ハイヤー協会・石川康夫会長「業界あげて反対を表明している」

県内のタクシー会社の団体、県ハイヤー協会の石川会長は、ライドシェア導入が「安心・安全の危機につながる」と強調します。

県ハイヤー協会・石川康夫会長「(タクシーは)毎年車検、3か月ごとの法令点検を受けながら、安全対策には万全の対策をとっている。そのために投資している。それが一般車両からすれば、そういう安全対策がないので、安心安全からすれば我々は反対」
また、ライドシェアで運転するドライバーについても「万が一事故を起こしたとき補償などをどう対応するのか?」と疑問を投げかけます。
一方で石川会長は、公共交通が弱い郡部などでは、共存共栄の可能性もあると言います。
県ハイヤー協会・石川康夫会長「山形県においても、郡部の方をみれば、自家用車有償運送という名目で、我々が関わった中で認めているものがある。(ライドシェアが)どういう中身になるかによって(対応が)変わってくると思う」
石川会長は「今後の政府の説明や対応を注視していきたい」としています。

改めて、石川会長の話を整理すると、課題としては車やドライバーの安全性ということがあります。一方、地域交通が十分でない地域にとっては地域の重要な足となり、タクシーとの共存の可能性を示しています。