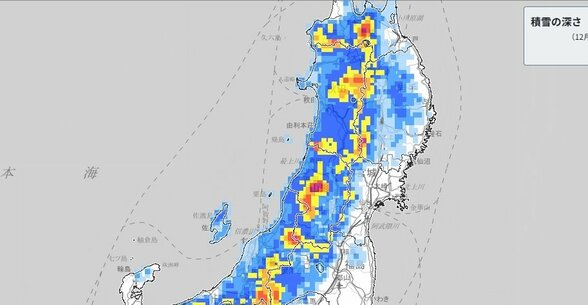地震で被災した富山県氷見市の復興のあり方を話し合う会議が23日開かれ、公費解体の現状や北大町の復興プランなどが示されました。

会議には氷見市の菊地正寛市長や専門家、地域住民らが参加しました。
なかでは市の担当者が8月末の時点で公費解体の申請があった953棟のうち約7割にあたる637棟で解体が完了した現状を報告。
市は11月には解体が困難な29棟を除くすべての建物で公費解体が完了する予定だとしています。
また会議では液状化の被害を受けた北大町地区について、金沢工業大学の蜂谷俊雄教授らが復興プランが示しました。

提案では、隣接する家屋が多く地震の揺れで互いの外壁や屋根が被害を受けた事例を踏まえ家屋の間に通り抜ける通路を整備する案が示されたほか、ひみ番屋街と連携した宿泊型レストラン「オーベルジュ」を誘致し、賑わいを創出する案などが示されました。
県内の建築家らとともに約1年半かけて考えたという蜂谷教授。
住民が共通の復興イメージを持つきっかけになってほしいと語ります。
金沢工業大学 蜂谷俊雄教授
「地域の方が共通の目標・夢を持つことが重要。あの災害をみんなで力を合わせて復旧・復興させたんだというその夢が大事だし、そのプロセスもまちづくりでは大事。結果の画だけでなく、それが毎回毎回更新されていって、いろんな方がいろんな意見を言う。それが大きな街のエネルギーになっていくと思う」
氷見市は今後、復興後のまちづくりについて、今年度中に方向性を決めたいとしています。