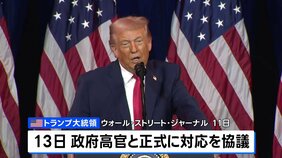■「ため池」活用した「水上太陽光発電」で農業に貢献
再エネ施設の適地の一つとして、宮城県の村井知事が挙げているのが、西日本を中心に広がりつつある「ため池」を活用した水上太陽光発電です。

今年4月から運用を開始した兵庫県の百丁場池太陽光発電所では、農業用ため池の浮島の上で太陽光パネルが黒く輝きます。発電量は、年間▼90万キロワットで、一般家庭およそ▼250世帯分が賄える計算です。
事業者のUPDATER(みんな電力)の梶山喜規取締役は、「再エネ事業は地域貢献につながる」といいます。

UPDATER(みんな電力)梶山喜規取締役:
「ため池自体が上に太陽光を置くと、夏場でも水温があまり上がらないため、水草が茂るのを防止する効果がある。加えて我々が重視したのは、ため池の維持管理自体が農業従事者の高齢化もあって社会問題化している。そこの助けの一つになれば」
■「津波被害の空き地」利用し、電力の「地産地消」に挑戦
また、消費者が再エネ施設を設置し、電力の「地産地消」を目指す取り組みも始まっています。
仙台市若林区の沿岸からおよそ1キロ。仙台市のNPO法人は津波被害を受けて移転した住民から空き地となっていた350坪の土地を借り受けました。周囲に遮るものはなく、太陽光が降り注ぎます。

太陽光パネルは、脱原発を掲げる「NPO法人きらきら発電・市民共同発電所」が市民からの出資金や寄付金を元手に設置しました。2015年9月から稼働していて、朝8時半から午後2時半までの6時間位で最大▼50キロワットの発電量があるそうです。
NPO法人の水戸部秀利理事長は、消費者によるエネルギーの「地産地消」だといいます。

NPO法人きらきら発電・市民共同発電所 水戸部秀利理事長:
「こういう設備をつくるにはお金がかかる。お金をどこから工面するかとなると、お金のある大手の資本とか、場合によっては海外資本がどんと入って来て、山を削ってします。しかし、そういう形ではなく、小さな努力が積み重なってエネルギーの地産地消を生み出していくというのが本来の良いやり方ではないか」
再エネ新税は、再エネ施設が地域と共生するための処方箋たりうるのでしょうか。
一橋大学大学院・山下英俊准教授(環境・資源経済学):
「本当にこの税が有効に導入できるようになるには、ここからどう具体的な制度化、詳細を詰めていくかというのが大きなポイントになるのではないか」
村井知事は、そのためにも適地には、積極的に再エネ施設を増やしたい考えです。
村井知事:
「例えば、現在、県民の皆さんからいただいている『みやぎ環境税』などを使いながら、ため池に太陽光パネルを設置する、あるいは、耕作放棄地に太陽光パネル設置するということを進めていきたい」
国は2050年までに温室効果ガスの排出量ゼロ、「カーボンニュートラル」の達成を掲げています。目標達成に向け、県の新たな取り組みが動き出します。