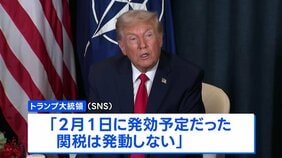東北電力は、東日本大震災以降運転を停止している宮城県にある女川原子力発電所について、29日夜、2号機の原子炉を起動させ、11月7日にも発電を再開する予定です。原子炉が起動すれば、震災後、東日本の原発では初めてで、被災地の原発が動くということでもあります。専門家は「極めて大きな一歩」と評価したうえで、立地地域の発展のため国や電力会社が努力する必要があると指摘します。
東北大学 竹内純子特任教授:
「日本のエネルギー政策上は極めて大きな一歩であると言える」

エネルギー政策が専門の東北大学・竹内純子特任教授は、日本のエネルギー自給率を高めるために原発は欠かせないと指摘します。
東北大学 竹内純子特任教授:
「よく再エネか原子力かと日本では言われるが、日本において再エネか原子力かを選択するほどの余裕はなくて、両方とも貴重な自給のエネルギーかつ脱炭素のエネルギーということで、両方を使っていかないと日本の経済、生活を支えるということは難しい。日本は1億2000万人からの人が住んでいて、製造業主体の経済なので、電力の消費量も世界で5番目くらいに大きい国。それだけ電気を使うボリュームがあるとなると、再生可能エネルギーで全てを賄うというのは現実的ではない」
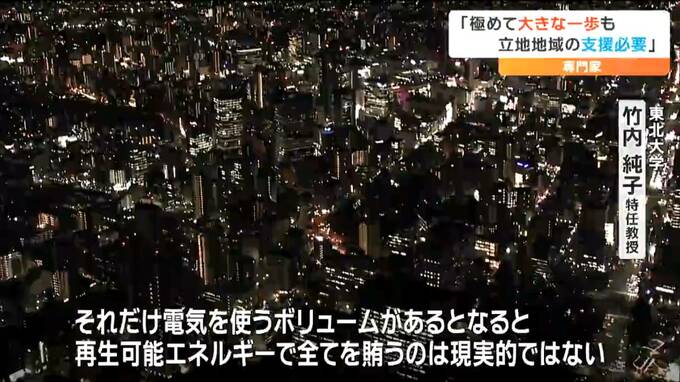
原発を動かすことは、電気料金の高騰対策にもなると言います。
東北大学 竹内純子特任教授:
「まだ1基しか稼働しないということだと、これによって東北地域の電気代が目に見えて下がるかというところまでのインパクトが期待できるかは疑問符だが、複数其が稼働している九州や関西が他の日本の地域と比べると家庭用の電気料金でも3割程度は安い」
一方で、国や社会のために事故などのリスクを負うこととなる立地地域には、十分な支援をすることが必要だと話します。

東北大学 竹内純子特任教授:
「東日本大震災でかなり歴史的な節目があって、改めて原子力発電所というものが日本に必要だから稼働するということになるので、原子力防災という文脈だけではなくて、原子力発電所がある地域が、地域として発展していくような支援策を国が講じる必要がある。発電事業者(東北電力)も入り込んで立地地域をどういう風に発展させていくか、持続可能な社会にしていくかを発電事業者も入って一緒に考えていくことを将来的にはやってほしい」