日本銀行は7月31日、今年2回目の利上げを決めました。専門家は、実体経済への影響は限定的とする一方、心理的な不安が景気の冷え込みに繋がる可能性を懸念しています。
日銀は、0から0.1%程度としてきた短期金利の誘導目標を1日から0.25%に引き上げました。3月のマイナス金利解除以来となる今年2回目の利上げに街の人は…。
「ローンがあるので、変わってきますよね、今後。どのくらい変わってくるのかまだわからないが。不安は不安」
「預金の利息が上がるでしょうから、その分はプラスになると思う」
「車のローンもないし家のローンもない。貯金も何千万円もあるわけではないし『そんなに変わる?」』って感じ」

金利が上がれば、住宅ローンを抱える家庭にとっては返済負担が多くなります。しかし、経済の専門家は「すぐに家計への負担が増すわけではない」と話します。
七十七リサーチ&コンサルティング 田口庸友首席エコノミスト:
「実際に返済額が上がるのはもう少し先、早くても年明け以降という(住宅ローンの)契約が多いのではないか。上がる金額も、さまざまな調整が働いて、すぐに大きく上がるということは考えにくい。家計に影響を及ぼすのはまだ先」
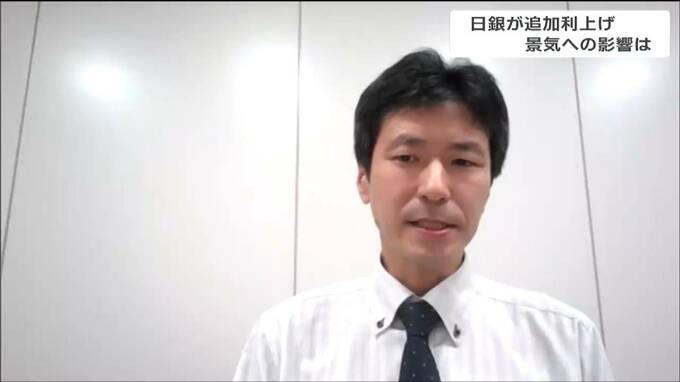
また、利上げを受けて1日は円高ドル安が加速し、一時1ドル148円台半ばにまで上昇しました。一般的に円高は輸入品の価格を下げるとされるものの、専門家は「消費者物価への影響は限定的」と話します。
七十七リサーチ&コンサルティング 田口庸友首席エコノミスト:
「(為替が)川下の消費者物価に影響を及ぼすには、かなりタイムラグがある。3か月から半年。また、為替だけではなく、賃上げを進めたことで人件費の価格転嫁が進んでくる。(円高が)消費者物価の高騰を抑える要因になるかというと、上がりすぎるのを防ぐという効果はあっても、下げるまではいかないのでは」
こうした目に見える影響よりも最も懸念されるのは消費者や企業の「心理的な不安」だと言います。
七十七リサーチ&コンサルティング 田口庸友首席エコノミスト:
「金利が上がるのが久しぶりなので、『この先どうなるのか』という不安感がある。家計であれば節約志向を強める、企業であれば投資などを控えるということが起きる可能性がある。実体経済以上に、心理的な不安による経済へのブレーキの方が影響が大きいのでは」










