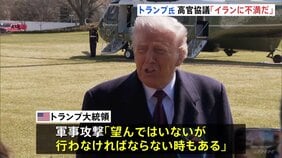奈良時代の切ない遠距離恋愛「相聞歌」

中臣宅守(なかとみのやかもり)と狭野弟上娘子(さののおとかみのおとめ)の2人は、宅守が罰を受け、地方に流されることになり、遠距離恋愛を強いられてしまいます。宅守の旅立ちに際して、弟上娘子は次のような激しい想いを歌にしています。
「君が行く 道の長手を繰り畳ね 焼き滅ぼさむ 天の火もがも」
あなたが行く長い道のりを、畳み重ねて焼き滅ぼしてしまうような、天の激しい炎があったらいいのに(万葉集 巻十五より)
これに対し、宅守は…
「畏みと 告らずありしをみ越路の 手向けに立ちて 妹が名告りつ」
神を畏れて口に出さなかったが、越前へと向かうこの道の頂上に立ち、がまんできずに愛しい人の名(弟上娘子)を口に出してしまった(万葉集 巻十五より ※当時は人の名前をみだりに口にだすと、災がもたらされると信じられていました)
という歌で別れの辛さと寂しさを表現しています。

宅守と弟上娘子のように、恋愛関係にある男女のほかに、親子など親しい者の間で互いの思いを伝えるために詠んだ歌のことを「相聞歌」といいます。当時は、自分の気持ちを込めた歌をしたためた手紙を送り合うことで、互いの気持ちを確認していたということです。宅守は流刑に際して、弟上娘子への想いをつづった計4つの歌を残しました。