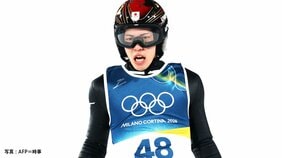学校「計画、引率に不備」
西豊田小は当初、別のルートでの下山を予定していた。水ヶ塚公園駐車場ではなく高鉢駐車場に向かうルートだ。

6月、教員はガイドと共に下見に出掛けた。高鉢駐車場のトイレが故障中と知り、7月下旬、水ヶ塚公園駐車場に向かうルートへの変更を決定。夏休み期間中に教員2人が下見で歩いたという。
夏休み明けの8月下旬、教員は5年生にルートの変更を伝えた。児童が当日持ち歩く「しおり」の行程表は差し替えず、旅行日程を事前に把握する立場にある静岡市教育委員会と保護者へも変更を伝えていなかった。
自然体験学習とリスクマネジメントに詳しい静岡大の村越真教授は、「ルールに則って市教委に報告すべきだった」としながらも、「ハイキングのルートは天候などに応じて事前に変わることはよくある。変更自体が遭難に直結したわけではない」とみている。
学校によると、5年生の1泊2日の自然体験教室は2020年度まで、静岡市葵区の井川で行っていた。大雨が降ると行き来が難しくなるなどの理由で、2021年度以降は富士宮市の朝霧を拠点に実施。富士山ハイキングは今回が初めてだった。
遭難事案を受けて同校は9月2日と9日に保護者説明会を開いた。保護者からハイキングの目的を問われた校長は、「自然の美しさ、厳しさに出会ってほしいと考えた」と答えた。
水ヶ塚公園駐車場へ向かう「須山口登山歩道」は、下るにつれて樹林や草花の様相が刻々と変化する。多様な昆虫に出会え、鳥のさえずりも聞こえる。ゆとりをもって歩けば、高山ならではの豊かな自然を楽しめる。
一方、足元には大小の尖った石や岩、木の根があり、記者は何度も滑ったりつまづいたりして転びそうになった。足の疲労も積み重なる。山に慣れていない人にとっては、歩くだけで精一杯かもしれない。午後になれば、人とすれ違うこともほとんどなくなる。道に迷った児童が感じた不安は計り知れない。
校長は保護者を前に、「計画、引率に不備があり、不安や恐怖を感じたお子様、保護者の皆さまに深くお詫びします」と陳謝した。
<全2回(#1/#2)のうちの1回目>