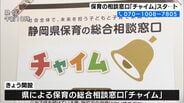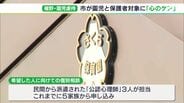元保育士3人が逮捕された静岡県裾野市の「さくら保育園」での虐待事件は、他の保育施設にも衝撃を与えました。虐待を見逃さないためには、どうしたらいいのか。保育士同士のコミュニケーションが大きなカギになります。
静岡市葵区の「hugくむ保育園 長沼」は、0~2歳の園児16人を預かる小規模保育所です。
<hugくむ保育園 長沼 本橋輝明園長>
「自我が芽生える時期なので、自我の芽生えは自分の思いを周りに投げかける時期。それにきちんと応えなければならない」
1歳や2歳は特に歩き始めたり、しゃべり始めたりして、目が離せない時期。切れ目のない保育で子どもの成長と安全を見守りますが、裾野で起きた虐待事件は、同じ世代の子どもを預かるこちらの保育園にもショックを与えました。
<hugくむ保育園 長沼 本橋輝明園長>
「虐待する人は子どもを思い通りに動かしたい、自分がきちんと保育できていることをみせたいとか、大人の都合でやってしまうことが多い」
「さくら保育園」で逮捕された保育士の1人は、事件のきっかけが「思い通りに動かない園児の行動だった」と話しています。また、これまでの調査で、別の職員が虐待行為を見て見ぬふりをする場面があったことも分かっています。
虐待を防ぐためには、保育士のストレスを減らし、風通しを良くする必要があり、こちらの保育園では職員同士のコミュニケーション改革を進めています。
<hugくむ保育園 長沼 深澤志織保育士>
「だれがどの仕事を持っているか、期限が早いか遅いかなど、見えるところに、どの保育士がどの仕事を持っているか管理できるようにしている」
この園では、保育士同士が仕事を共有できるよう「見える化」を図っているほか、職員同士がSOSの合図をピースサインで送るなどの決めごとを実践。言いにくいことを少しでも減らすため、職員同士が話し合いをして対策を練ったのです。
<hugくむ保育園 長沼 本橋輝明園長>
「研修などを重ねることで常に細心の注意・意識を持つように職員はしている」
「適切な保育」とは…、子どもの成長を見守る保育の現場では試行錯誤が続いています。
全国のトップニュース
逃げた車は偽造ナンバー… 羽田1.9億円強盗未遂事件 上野の4億円強盗と同一犯の可能性も 多額の現金が運ばれる情報を事前に入手か

香港で日本円5800万円強盗 被害者は空港で荷物受け取りめぐり2人組と口論か 空港で容疑者1人逮捕

衆議院選挙 序盤の最新情勢を徹底解説 自民「単独過半数」うかがう勢い 一方で中道は大幅減か・・・結果左右する「公明票」の行方とは【edge23】

「口の中も血まみれに…」終わらない治療、失った金 “インプラントの名医”が患者から1億円超の現金詐取 千葉で起きた前代未聞の詐欺事件 逮捕につなげた被害者の執念

「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】

5年前は部員3人「声を出すのが恥ずかしく⋯」センバツ初出場・高知農業、21世紀枠で掴んだ“夢舞台”への切符【選抜高校野球2026】

「移民当局は出ていけ」全米でトランプ政権への抗議活動 ミネアポリスで相次ぐ発砲事件受け

次期FRB議長にウォーシュ元理事を指名 トランプ大統領「非常に賢く、とても優秀で、そして若い」