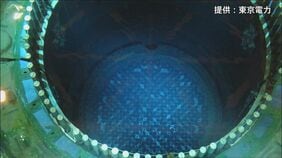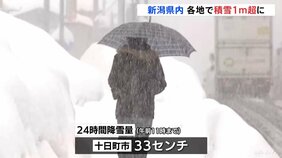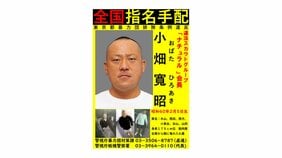さきごろ、防災訓練が3年ぶりに静岡県中部で開かれた。南海トラフ巨大地震の発生を想定した大規模な訓練には自衛隊の輸送機なども投入され、2万5000人が参加し地域の防災力向上に取り組んだ。
地域防災の担い手は自治会。そして、災害から命を守る「武器」が格納されているのが防災倉庫だ。しかし、倉庫の装備レベルは地域で一律ではない。自分の住む地域の倉庫は、隣町の倉庫より備えのレベルが低い場合もあるのだ。
これでは、倉庫を開いてみたら「役に立たないものばかり」という、まさに「防災倉庫ガチャ」。
静岡の大学生や高校生で立ち上げた防災NPO「New Universal Act」のメンバーが、地域の防災倉庫を訪ね、備えておきたい防災グッズを調査した。
イマドキの生活に合わせ更新

倉庫を見せてくれたのは、同市中心部からほど近い閑静な住宅街の自治会。会員数は約800人、ご多分に漏れず高齢者が多いと会長の戸田正明さんが説明してくれた。
幹線道路沿いに設置された防災倉庫を開けると、まず出てきたのがアルミ製の折りたたみ式リヤカー。「物資もそうなんだけど、けがをしたお年寄りなどを乗せて避難させる場面が多くなるのかな」と戸田さん。
以前あった頑丈だが重く、取り回しの悪い、昔ながらのリヤカーを更新したという。NPOのメンバーたちは初めてにも関わらず、数分で組み立て完了。女性メンバーを乗せて軽さを確かめていた。
この自治会は、防災用に会費を積み立て必要な機材を購入し、備品リストを全員で共有している。「最近そろえたんだよ」と紹介してくれたのが、大型のLEDライト、USBポートも備えたポータブルバッテリーと太陽光発電パネルだ。
「バッテリーはスマートフォンなどの充電もできるからね。パネルを広げてつないでおけば曇りの日でも充電するから便利だよ」日常を便利にする新技術は防災用具にも採用されている。戸田会長はウエブで最新情報をチェックしてイマドキの生活様式に合った機材を選んでいるという。
倉庫の奥からNPOメンバーが軽々と運び出したのは、ガソリンとガス缶の両方が使える発動発電機だ。すでに2台の発動発電機があるにも関わらず備えたという。
「ガソリンは劣化が早く、タンクに入れっぱなしにすると、ここぞって時に使えないんだよ。避難訓練の時に何度も苦労したから、入手も保管も簡単なガス缶も使える物をって。さらに、パソコンなどの精密機器も使えるようにインバーター式を選んだんだ」用意周到な戸田さん、劣化しない密閉缶入のガソリンもストックしていた。
訓練を重ねて育てる防災倉庫

住宅街の奥に、もう一つの倉庫があった。こちらには長机や大型テント、担架などが収められている。
「十数年前は、棒と毛布で簡易担架ができるからと、手作りしたんだけど、他県で人を運んでいるうちに壊れる事故が起きてからは使わないようにという指導がで出てね。折りたたみ式の担架を買ったんだけど、ちょっと持ってみなよ」
メンバーは戸田さんに促されて二人ががりで女性メンバーを運んでみたが、すぐに疲れて一旦休憩。「2人で1人を運ぶとせいぜい100㍍が限界。やはり4人は必要なんだよ」戸田さんも実際に訓練で使ってみて分かったという。
防災トイレは女性への配慮から積極的に導入を進めている。「昔は『そこらへんに穴を掘って』なんて、男性中心の考え方がまかり通っていたんだけど、今はそれじゃあダメ」。戸田さんは家庭でも備えてほしいとペール缶を使った防災トイレを住民に有償で斡旋しているという。NPOのメンバーも手際よくトイレとテントを組み立てて使い勝手を確かめていた。
「これは最近は使ってないな」と引っ張り出してきたのは1トンの水を貯められる組み立て式の貯水槽。水の確保は最も重要だと導入したものの、そもそも1トンもの水をどうやって入手し、衛生的に管理するのかなどさまざまな課題が明らかに。
その後、ペットボトルの普及など水の入手方法が多様化したため貯水槽の必要性は低くなったという。揃えた装備は使ってみる。訓練を通して得られた知見を新たな装備選定に生かすことで「役に立つ防災倉庫」に育っていくという。
さまざまな装備を確認したNPOのメンバーたち。中高生時代には、嫌々参加していたという地域の防災訓練への関心も高まった。NPOの藤本湧磨理事長(大学2年)は「災害は明るい時間帯に起きるとは限らないので、夕方からスタートして暗闇の中どのように明かりや眠る場所を確保するのかを確かめる、夜間訓練が必要だと感じました」と話す。
女性メンバーの小杉和可奈さん(高校2年)は、「指摘されるまでトイレの大事さに気が付きませんでした。もっと女性が声を出して準備・対応しなければと感じます」と意識を高くしたようだ。ジュニア防災士の資格を持つ興津秀太さん(高校1年)は「防災装備はみんなが使えて初めて役に立つ。遠巻きに見守っているだけの防災訓練はもう終わりにしなければ」と訴えた。
広げないで、防災力の格差

静岡市内で自治会や学校などに防災のアドバイスを行っている防災指導員の藤浪清さんは、この自治会の防災倉庫に”満点”を付けた。
「自分たちの地域で起こりやすい被害を想定して、それに対応する装備をしている点が評価できる。情報機器の充電など、現代の生活に必要なものをよく勉強している。さらに備品リストを共有しているので、町内の全員が倉庫に何があるのかが分かるのも便利。発災時に防災担当役員が無事という保証はどこにもない」
その上で防災倉庫の備えの格差に警告を鳴らす。「このような防災倉庫はまれ、と思っていい。自治会長や防災担当者がどれだけ地域の防災を考えているかで倉庫のレベルは決まるが、全員が熱心というわけではない。コロナ禍で防災訓練が中止になり、その間に役員が変わるなどして、災害への心構えや、問題意識などが引き継がれていない自治会も少なくない。発災時に倉庫の扉を開けたら役立つものがなくて驚かないよう、中身の確認はまめにやったほうがいい」
※この記事は「静岡新聞・SBS防災減災プロジェクトTeamBuddy 2022高校生防災特集号」を再編集したものです。