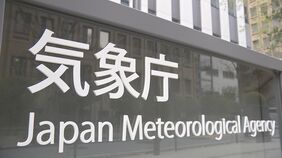かつて、機(はた)織りが盛んだった長野県佐久地域。
江戸時代から昭和の初めにかけて女性が家族のために織った織物は、「うち織(おり)」と呼ばれています。
「うち織」の文化を地域の伝統として後世に残そうと、文化財への登録に向けた活動が始まっています。
繭からとった細い糸が、職人技のようにきめ細かく織り込まれています。
一般家庭の女性たちが100年ほど前に作ったもので、自分の家、「うち」で使うために機織りをして作ったことから、「うち織(おり)」と呼ばれています。
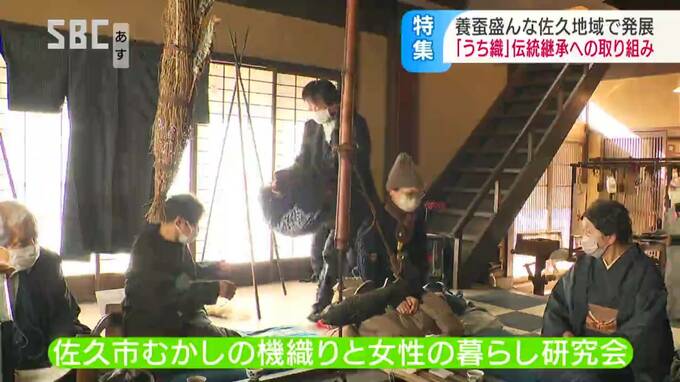
時代とともに「うち織」を知る人が減るなか、文化を伝承しようと取り組むのが「佐久市むかしの機織りと女性の暮らし研究会」。
地元の呉服店や学者などがメンバーとなり「うち織」を市の民俗有形文化財に登録しようと活動しています。