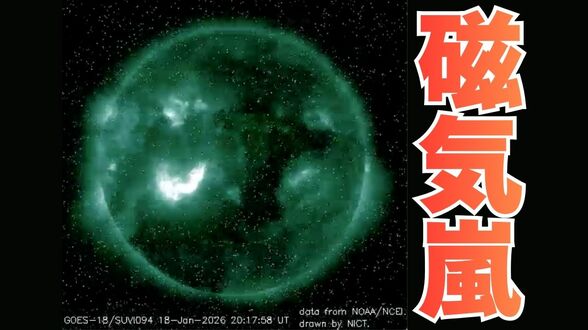自らが犠牲になり仲間を守る!
「とはいえ、成虫が毒を持っていることを他の生き物が初めから知っているわけではありません。
これは『学習』を利用した戦略で、もし天敵に食べられてしまった場合、その敵はアサギマダラの毒で体調を崩したり吐き出したりします。
そうして次からは『この美しく目立つチョウは食べられない』と覚えるため、仲間が狙われにくくなるのです」
毒を持たないのにアサギマダラにそっくりなチョウもいる
(大野竜徳さん)
「日本には定着していませんが、海外には毒を持たないのにアサギマダラにそっくり擬態する『カバシタアゲハ』というチョウも知られています(ベイツ型擬態)。
もっとも、仲間を守れても自分が犠牲になっては元も子もない気もしますね。
野外でアサギマダラなどの大型のチョウを観察すると、翅の一部がかじられたように傷つき、ぎこちなく飛ぶ個体に出会うことがあります。
これは鳥に襲われた痕跡で『ビークマーク』と呼ばれます。
しかし翅の少々の傷なら命を落とさず飛び続けることができます。
アサギマダラは大きな翅をもち、ひらひらと漂うような独特の飛び方で狙いをつけにくくし、逃げ切る余地を生み出しているのです。
目立つ姿ですが、自分の身は当然守りながら、もしもの時には自分の身を犠牲に仲間の身を守っているんですね」
アサギマダラの移動距離は1000キロ以上!? シーズンは?
(大野竜徳さん)
「そんなアサギマダラは本州では5〜6月、そして渡りのシーズンである9〜10月に姿を見せてくれます。特に秋は、寒い北から暖かい南へ南下する途中で、四国や九州、さらに大きく海を越えて沖縄や南西諸島、台湾へと向かいます。
その移動距離は1,000キロを超えることもあり、モンシロチョウやアゲハチョウでは考えられないほどの長旅です。
この旅を見守る人々も多く、各地で『マーキング調査』が行われています。
捕まえたチョウに印をつけ、他の場所で再捕獲されることで移動距離や経路が解明されます。
数百キロ離れた土地で再発見されることも珍しくありません」