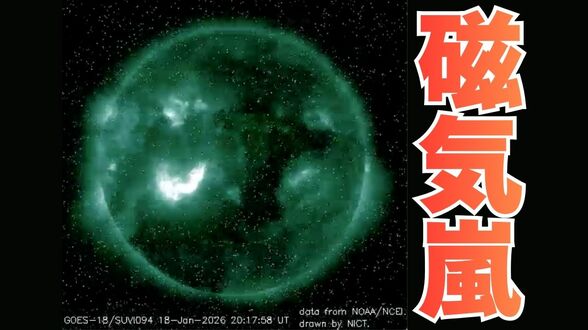「旅するチョウ」アサギマダラ
(大野竜徳さん)
「アサギマダラは『旅するチョウ』としても知られ、日本各地で多くの人々を魅了し、その姿を追いかける愛好者も少なくありません。
ただ美しいだけでなく、驚くべき生態や文化的なエピソードも秘めています。
一般的に、アサギマダラは春から夏にかけて本州や北海道で成育します。
幼虫は黒地に黄色と白の規則正しい斑模様をもち、頭部と尾部に一対ずつの突起を備えたイモムシです。
食草はキジョラン、イケマ、サクラランなどの植物で、これらを食べて成長します。
幼虫はいかにも警戒色といった派手な姿でとても目立つのですが、天敵からすると実はおいしくないイモムシです。
というのも、食草はキョウチクトウ科(昔の図鑑ではガガイモ科と記されています)の植物で、これらはアルカロイド系の毒をもちます」

毒を体内に蓄える!?
(大野竜徳さん)
「アサギマダラはこの毒を食草から取り込み、体内に蓄えているのです。
こうしてすくすく成長した幼虫は羽化し、あちこちの野山を飛び回ります。
成虫は写真のように花の蜜を好みます。
特にフジバカマやヒヨドリバナなどのキク科の花を好み、蜜に含まれるアルカロイド系の毒をさらに吸収して体内に蓄積します。
この毒成分であるピロリジジンアルカロイドは、仲間にモテるためのフェロモン生成にも使われます。
アサギマダラは一生を通じて植物の毒を自らの体に取り込み、巧みに利用しているのです」