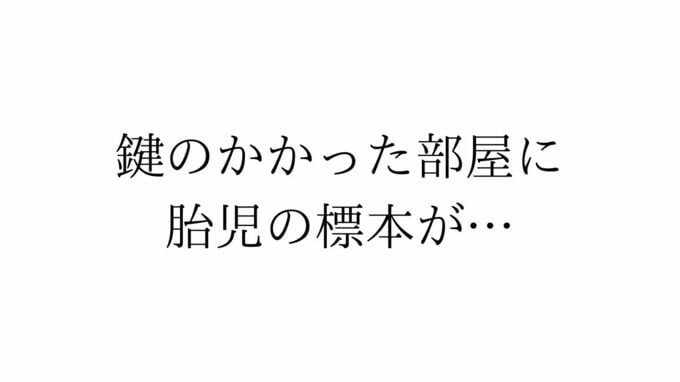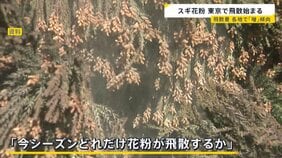ハンセン病はなぜ差別されたのか
長年、差別や偏見を受けてきた「ハンセン病」。
なぜ差別されてきたのか、法曹界はどのような役割を果たしてきたのかなどをテーマにした講演が、8月24日、「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」(岡山市北区表町)で開かれました。
ハンセン病訴訟に関わった弁護士の井上雅雄さんが講演しました。(全3回のうち第2回)
【菊池事件】「公開の原則を無視した法廷で死刑判決 」井上雅雄弁護士が語る「ハンセン病はなぜ差別されたのか」第1回(全3回)
「らい予防法」廃止へ 原告と弁護団が一緒に戦った
(井上雅雄弁護士)
「結局そこからなんですけども、療養所におられた知人男性が、九州地方弁護士会連合会、九弁連っていうんですけども、その大会の時に、書簡を送られました。
それをきっかけとして、九弁連の方で、ハンセン病の問題について、検討をするという形になり、その辺りからやっとやっと弁護士が動き始めた。
これが確か、らい予防法が廃止される1年前のことだったと思います。その動きの中で、厚生労働省の方も検討会を作って、廃止に繋がっていくという流れになっていきます。
実は、厚生労働省の中で、ハンセン病に携わっていた方の中にはですね、この法律はいけないと。早く廃止しなきゃいけないという風にずっと思っておられた方はいたようですが、なかなかそこまでいかない状況でした。
そして、1996年(平成8年)にらい予防法が廃止されるということになります」
「 福岡県で弁護士会が開いていた会合の中で、国賠訴訟したいと思っているけれども、やってくれる弁護士がいるのかという質問がありました。
その時に、徳田靖之弁護士がパネリストで出ていまして、九州だけでも100名以上の弁護士が関わってくれるはずだと回答したということで、そこから、国賠訴訟の流れが始まるということになったと聞いています。
結局1998年に、原告13人の方で、熊本地裁に提訴が行われました。集まった弁護士は137名と聞いています。
熊本で裁判が行われていきます。そういう中で徐々に原告の数も増えていって、熊本だけでやっていくよりも将来の全面解決を目指すということもあって、東京、瀬戸内の3箇所で裁判を起こしようという風に変わっていきます。
そして、1999年に、瀬戸内訴訟が岡山に提出されるということになります。私が関わったのは、瀬戸内訴訟提訴からになります」
「提訴前に、どういう形で原告の方々に呼びかけ、原告の方々に入ってもらうのか、誰が原告団長という形で立っていただけるのかといったようなことを、話を進めてました。
岡山でもやるよという話をするにあたって、瀬戸内弁護団は療養所に毎週のように週末は入るという形で、そこで原告たちと話をするということを始めました。
最初の時か2回目の時か忘れましたけども、原告と弁護士たちが夜一緒に酒を飲んで話していた時に言い合いになることもありました。
ハンセン病の裁判は、特に、原告の方々と一緒に戦うという、そういう側面が非常に強い裁判でして、やっぱりそこで本当に信頼される関係性を作らないとなかなか戦えないというのもよく分かりました」