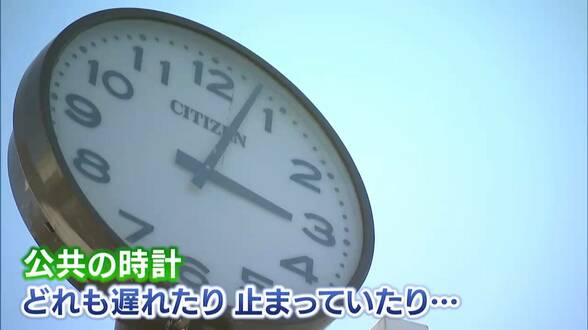■総延長4,000km、柵の設置は5年で90km…「すべてやるのは不可能に近い」

事故を防ぐ方法として最も一般的なのは「柵の設置」ですが…。

(岡山市道路港湾管理課 杉本章課長)
「相当な距離数がございますので、すべてやるっていうのは不可能に近い」。

岡山市では2016年度から「危険箇所」を定め、柵をつけるなどの対策を講じてきました。これまでに完成したのは約90キロ分。総延長の4000キロからみればわずかですが、それでも13億円ほどかかります。全ての用水路に対策を施すのは現実的ではなく、担当者も頭を悩ませています。
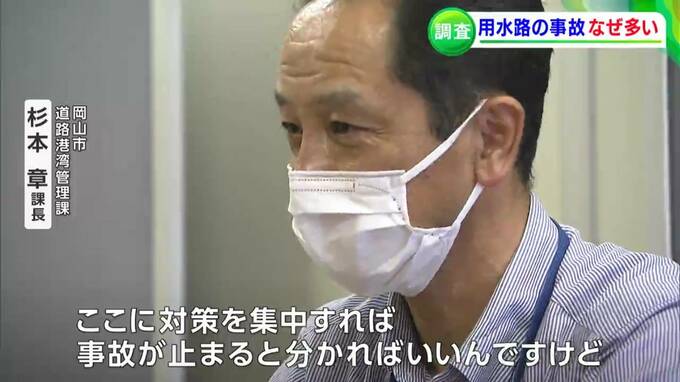
(岡山市道路港湾管理課 杉本章課長)
「『ここに対策を集中すれば、事故が止まるんだ』っていうところが分かればいいんですけど、広くどこでも事故の可能性がある」
■なぜ転落する? 侮れない「用水路の怖さ」

ハード対策に限界がある中、命を守るために何に気をつければいいのか。岡山県警の事故分析官に岡山市中区の死亡事故の現場で聞きました。


(岡山県警交通企画課 河本貴文交通事故分析官)
「この現場でいいますと、夜は本当に真っ暗な状態だと思うんですね。事故当時はライトはおそらくつけていたと思うんですけど、ちょっと考え事をしたりだとかで、簡単に自転車はすぐ向きが変わりますから。何かの弾みに落ちてしまったのでは」
さらに死因からも、『それほど深くないから』といって侮れない“用水路の怖さ”が見えてきます。

(岡山県警交通企画課 河本貴文交通事故分析官)
「死因は溺死。水を飲んでっていうのが半分くらい。半分くらいが頭を打って、脳挫傷とか。『ヘルメットで頭を守る』というのは有効だと思います」