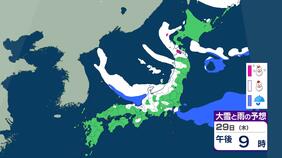◆よかった朝日コラム「天声人語」

やはり“8月ジャーナリズム”はとても大事だ、と思います。6紙の今朝の「1面コラム」を読みましたが、全部、戦争と平和の話で書いています。読んでみて一番印象に残ったのは、朝日新聞「天声人語」でした。
記者が子供のころ「あれは小学校5年生だったか、担任の栗原先生が一度だけ戦争の話をしてくれた」と書き出します。サイパンで生まれ育った先生は、9歳のときに米軍が上陸してきて、ジャングルの洞窟へ逃げ込んだ。飢えと渇きで眠れず、12日目に「ミソアリマス、デテコイ」という米兵たちの声が聞こえたそうです。「なんで味噌?」
『▼水あります、が片言でなまった。のどが渇いているのに味噌なんて、とだれも動かない。呼びかけは延々と繰り返された。ついに母が「死ぬ時はみな一緒」と投降を促す。朝から水を探しに出ていた父は、たぶん米軍に撃たれ、永遠に戻らなかった▼子どもは時に残酷だ。「ミソアリマス」は、クラスの男子のはやり言葉になった。でもおかげで、40年たってもあの授業は忘れない』
(朝日新聞8月15日朝刊「天声人語」より)
自己体験の中から出てきた言葉です。先生から聞いた「味噌あります」が流行り言葉になった。どれほど残酷なことだったか、と実体験として書いている。コラムの最後は「先生から預かった話を皆さんにお渡しする」。口で語り、口で語られたことを聞く。それが大事なことなんじゃないかというこのコラム、とてもいいなと思いました。
◆社説で「新しい戦前」に触れた新聞

西日本新聞の1面のトップは「安全保障を考える」という企画で、見出しは「もの言えぬ『新しい戦前』」。昨年末にテレビ番組『徹子の部屋』でタモリさんが言った言葉です。「来年はどんな年になりますかね?」と聞かれ、「新しい戦前になるんじゃないですかね」と言ったんですよね。私も見ましたけど、びっくりしました。
やはりタモリさんは優れていますね。「戦後が終わる」ということは、「戦前の始まり」かもしれません。西日本新聞は社説でも「新しい戦前」について触れていましたし、日経新聞も社説で書いています。
『今年、その「戦前」に光があたった。きっかけはタレントのタモリさんが語った「新しい戦前」という時代認識に共感が広がったことだ』(日経新聞8月15日朝刊社説より)
※生放送では言い損ねましたが、毎日新聞1面コラム「余録」でも、「新しい戦前」に触れています。
今、米中対立だったり、ウクライナ戦争だったり、いろいろな対立がある中で、戦争のことをこう考える人が増えている、ということ。防衛力の増強もありますし、私達の暮らす日本もそのものも、新しい戦前に入ってきたのではないかと言われると、ドキッとしますよね。
善し悪し、いろいろな意見があるでしょうけど、時代がそういう大きな変化を迎えている可能性が高く、「後で思ったら、タモリさんの言った通りだったな」ということになるかもしれません。そんな年に私たちが生きている、ということを今日の紙面を見ても考えます。今朝の朝刊各紙を見てみると、いろいろなことを考えるんじゃないでしょうか。
◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)
1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材してラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。