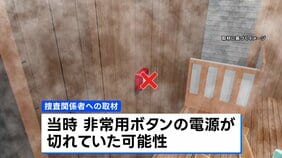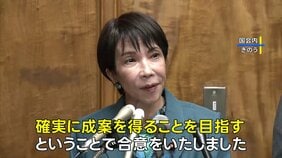つらい決断「事業の継続いまのスキームでは難しい」
帰国後に、改めて協力企業の担当者と話し合ったが、やはり現在のスキームでの事業の継続は難しいという結論にしか至らなかった。
問題は買取価格の低さだけではなかった。
価格が多少低くても、大量に収穫したものをすべて買い取ってくれるのであれば、スケールメリットで補えると考え、その道も探っていた。
だからこそ、輸送ルートを確立して大規模な栽培・輸送に対応するための手立てなどを企業側には検討してほしかったのだ。
しかし、企業側が予定しているオクラ事業の規模は、現時点ではそれに見合うものではなく、大量生産できたとしても全量を買い取ることはできないという。
企業側としても、この事業の未来についてビジョンを描けていないことは明らかで、私は担当者に、「事業の将来性も示せないまま、提示されている値段でオクラを売ってくれと、私から彼らに伝えることはできない」と告げた。

地元の市場にもっていけば倍近い値段で買い取ってくれるのに、わざわざ安く売るように強制することはできない。
支援のために取り組んでいる以上、こちらとしても譲れない主張ではあったが、それでもこの決断を伝えるのはつらかった。
それは、この協力企業との決別を意味することがわかっていたからだ。
野菜を買い取れないということは、企業にとってはここまでの投資が無駄になるわけで、受け入れられるはずがない。
買取価格を見直してでも継続の道を探るか、この事業自体をきっぱりとやめてしまうか、そのどちらかを決断せざるを得なくなる。
そのことを十分に理解したうえでの通告だった。
メッセージを送ってから2時間もたたずに、担当者から事業の撤退を伝える連絡が来た。
企業内では、とっくにその結論は出ていたのかもしれない。