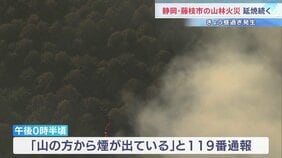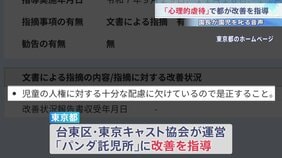日本勢が金メダル20個を含む45個のメダルを獲得するなど盛り上がりをみせたパリオリンピックが閉幕した。かつて東京大会で毎日新聞社のオリンピック・パラリンピック室長を務めた山本修司氏が8月16日、RKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演し、あえて日本がメダルに届かなかった団体球技、特にサッカーに焦点をあててパリ大会を総括した。
団体競技で日本は「92年ぶりの快挙」
私が現在勤務している毎日新聞出版は今日(8月16日)、パリオリンピック総集編のムック本を発売しますが、表紙は悩んだ末にやり投げの北口榛花選手にしました。そんな中でなぜサッカーの話かということですが、北口選手も含めていろんな競技で「海外で活躍する選手が増えてレベルが上がった」と分析される場面が多い中で、私はそんな単純な構図ではないことをお知らせしたいと思ったわけです。
団体球技は振るわなかったと思われがちで、確かにバスケットやバレーボール、サッカーなどが期待された中でベスト8が最高でした。それでも、実は全ての団体球技に、日本は少なくとも男女どちらかは出場を果たしています。比較するのはどうかとは思うのですが、これはホッケーと水球の2競技のみが行われた1932年ロサンゼルス大会以来ということで、ある意味92年ぶりの“快挙”だったのです。
Jリーグ発足で裾野が広がった日本のサッカー
そういった意味では、日本の球技はなかなかのレベルということですが、団体球技の中で私はサッカーで選手も審判も指導者も経験したので、オリンピックが終わったこのタイミングで、例としてサッカーを取り上げます。
日本サッカーはいまでこそ、当たり前のようにワールドカップやオリンピックなど国際大会に出場していますし、入賞やメダルを期待されるまでになり、選手も優勝や金メダルといった目標を口にしています。
ですが、私がサッカーを始めた半世紀前には、1968年のメキシコオリンピックで銅メダルを取った実績はあったものの、その後オリンピックになかなか出場さえできない、ワールカップに至っては出るのが夢のまた夢といった時代でもありました。
日本のサッカーの転機は何と言ってもプロのサッカーリーグ、Jリーグの発足です。1993年のことですが、それまでの企業主体ではなく、地域主体でクラブを運営していく形になっており、プロチームを頂点に、ユースやジュニアユースのチームを持ち、小さいときから体系的に高度な練習をする形が出来上がりました。
また多くの選手がヨーロッパや南米などサッカー先進地に渡って活躍するようになり、そういった選手が日本代表を形成するから強くなったのは間違いないのですが、私が指摘したいのはそこではないんです。
ユースや強豪といわれる学校に入れない普通の子供たちが、レベルの高い練習をできる環境になり、サッカーの裾野が想像以上に広がったことが大きな要因になったと考えています。山の頂点は裾野が広ければ広いほど高くなりますので、トップレベルに至らない大半の子供たちがレベルを上げたことが、今のように日本のサッカーが欧州などに迫る高さの山を築いたと私は思うのです。