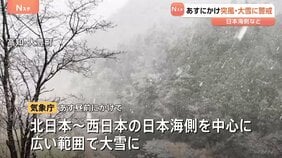言葉の意味をスマホ、辞書それぞれで調べると…
田畑:これは、例えばスマホで癒しの映像を見るとか、そういうときだったらまだ分かるんですが、何か調べ物をしているとか、どういう使い道でも同じような結果なんですか。
川島:はい、例えば難しい言葉の意味を調べたりとか、あとは文章を書いたりとか。それもチャットのような短いものではなく、メールぐらい長い文章を考えて書いてもらうということをしたんですけれども、全く働かなかったです。
田畑:言葉一つ調べるにも、辞書を引くというアナログなやり方と、スマートフォンでパパッと短時間で調べるのとでは、脳に残る具合も違うってことですか。
川島:はい、脳が働かないだけではありません。実験で大学生に「覚えろ」ということは言わずに「言葉の意味調べだけしてください」と伝え、いくつかの言葉の意味を調べてもらう際、辞書を使ったときと、スマホを使ったときとで比べてみたんです。すると、スマホを使ったときは、その後に「さっき調べた言葉の意味をもう一度思い出して」という質問をしたところ、スマホを使って調べた言葉の意味は一つも思い出せなかったんですね。要は記憶に残らないんです。一方、紙の辞書で引いた言葉の意味は、半数以上思い出すことができました。
“自分の時間を使われない”スマホの使い方
田畑:スマートフォンのどういうところが脳に良くないんですか。
川島:実は正確にはよくわかっていません。一番考えられるのは、スマートフォンを使っているとき、どうやら脳はうまく集中できていないということがポイントかなと思っています。
田畑:先生も当然スマートフォンは使いますよね。
川島:はい、使っています。
田畑:例えば使う頻度を減らすとか、何か工夫はしているんですか。
川島:僕は道具として使っています。例えば、電車の切符を予約したりとか、出張したときに、目的地に向かうルートを調べたりとか。あとは、学生との連絡に使っています。一方で、例えば時間が余ったからそれで動画を観たり、ゲームをしたりという使い方は一切してないです。
田畑:必要なときにだけ最小限で使うようにしているわけですね。
川島:イメージとしてはスマホを使っているんです。スマホに自分の時間を使われないように意識しています。
田畑:なるほど。依存、支配なんていう言葉もありますが、そうならないようにしているわけですね。あくまでコントロールしているのは自分だと。
川島:はい、その通りです。
田畑:ただこのスマートフォン、タブレットなども含めてですが、今、特にコロナ禍になって、GIGAスクール構想を早めたことによって、学校教育の場で子供たちに普及するスピードも早まりましたよね。明日以降、スマートフォンが学力にどう影響を与えるのか、そしてどう向き合っていけばいいのか、お話を伺っていきます。明日もよろしくお願いします。
川島:はい、よろしくお願いいたします。