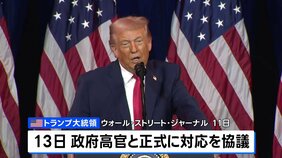ドイツモデル…柔軟な働き方が賃上げの鍵に
加藤氏は、雇用制度改革のモデルとしてドイツを紹介する。2000年ごろまでは日本と似た雇用形態だったが、現在は「正規雇用と非正規雇用の区別がない」という。したがって、仕事の種類で給与水準が決まる。
例えば、小売店でのレジや在庫管理などの業務内容で賃金水準が設定されており、個々人の労働時間によって支払われる給料が決まる。会社が決めるのは仕事の内容とそれに見合う給料。一方、個人の時間の使い方は各個人が決めるというのが考え方の基本だ。
労働時間や働き方はあくまでも個々人が自分の事情に応じて決めることで、「子育てや趣味に合わせた働き方が可能になる」と加藤氏は語る。実際に、警察官や裁判官にもパート勤務が存在し、大手自動車メーカーでは2人の女性が人事部長職をシェアするなど、幅広い分野で柔軟な就労が実現しているという。
「この方式だと、正規社員が『この仕事は自分が全部やらなければならない』『休みを取りにくい』という状況も変えられる。結果として正社員も楽になるし、自由になる」と、制度のメリットを強調する。こういった方式は、ドイツのみならずEUでは一般的だ。
賃上げの実現に向けて、加藤氏は「雇用や給与の支払い方に関する基本的な制度は政府が決められる。『個人の時間の使い方は個人が決める』という大原則を打ち出せば、正規・非正規の区別は不要になる。そこを変えれば、企業も支払い方を見直し、給与水準も自然と上がっていく」と説明。雇用制度の抜本的な改革こそが、生活支援の“本質的な”処方箋になると訴えている。

加藤秀樹(構想日本代表)
京都大学経済学部卒業後、1973年大蔵省入省。証券局、主税局、国際金融局、財政金融研究所などを歴任。1997年4月、非営利独立のシンクタンク「構想日本」を設立。2009年に政府の行政刷新会議の事務局長に起用され、国レベルの事業仕分けに取り組む。公益財団法人国際連合協会評議員、一般財団法人地球・人間環境フォーラム評議員などを務める。