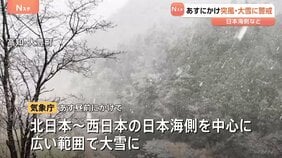体内でタンパク質が糖分と結合し、細胞や組織を劣化させる「糖化」。老化を促進する要因として知られていて、その進行を可視化させた大分市の中学生が、日本最大の化学の学会「日本化学会」で発表しました。中学生としての登壇は異例で、来場した他の研究者からも注目を集めました。
学会で発表したのは、科学体験塾「うちらぼ」(大分・別府市)に通う中学2年の宮崎香帆さん。塾代表の加世田国与士さんの勧めで、糖化の研究に取り組んでいます。

糖化とは、体内でタンパク質と糖が結びつき、AGE=終末糖化産物を生成する現象で、老化や病気に影響を及ぼすとされています。
宮崎さんは、ゼラチン液にブドウ糖などを混ぜる実験を繰り返し、糖化が進行する際に変化する色に着目。色の違いを0から100までに数値化した「色見表」を独自に作成しました。

宮崎さん:
「糖化から多くの人を助けたいと思ってこの実験をすることにしました。いろんな色を作らないといけないところが大変でした。色見表をもっと改善して、多くの人が糖化を知ることができるようにしていきたいです」
宮崎さんは、3月に開催された日本化学会の第105春季年会で、これまでの研究成果を発表。中高生も参加可能ですが、中学生の登壇は異例です。会場では『この研究は中学生によるものです』と紹介されると、どよめきが起こったといいます。

宮崎さん:
「糖化は、糖尿病やがん、アルツハイマー病などいろんな病気に関係していることがわかってきています。学校で習うことはなく、あまり知られていないので、誰もが理解できる簡単な実験方法を伝えました」
7分という時間制限の中、宮崎さんは緊張しながらも、来場者からの質問に対し、冷静に応じました。
加世田国与士代表:
「研究のポイントを自分の言葉で伝えていたので、すごいなという感じで、先生たちが前のめりになっていました」
およそ150年の歴史ある学会の大舞台で研究発表した香帆さん。早くも次の課題に向けて構想を練っています。
宮崎さん:
「質問に素早く答えるところが前より良くなったと思うし、期待に応えられるようになったと思います。今後は糖化の進行を遅らせたり、止めたりする物質を探してみたいし、固形の食べ物を使って実験をしたいです」