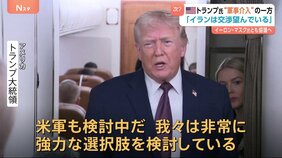震源に一番近い観測計からデータが取れない
気象庁や国土交通省の港湾局などは、日本全国の沿岸に津波の高さを測る装置を設置していて、24時間体制で監視しています。

能登半島地震では金沢で80センチ、七尾港で54センチの津波を観測しました。一方、気象庁が当初「1.2メートル以上」と発表した輪島港は、後日観測機器に不備があったとしてデータが取り消されたほか、珠洲市長橋の観測計は地震直後からデータが受信できなくなりました。何が起きていたのでしょうか。

震源に最も近い津波観測計がある珠洲市の長橋漁港。実はこの場所は地震で約2.8メートルも隆起しました。漁港近くに暮らす坂石藤雄さん(72)もまた「潮が引いたから絶対これは大きな津波が来ると思った。まさか隆起したなんて誰も思っていなかった」と話しました。

気象庁が受信できなくなった珠洲市長橋のデータを後日回収したところ、地震が発生した午後4時10分の2分後から急激に水位が下がり、マイナス1.2メートルのところでデータが途絶えていたことが分かりました。

隆起によって海底があらわになり、津波の高さを正しく観測できない「欠測」の状態に陥ったのです。