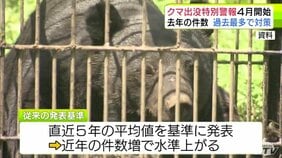実は、1998年に国は生食用の牛肉と馬肉について処理方法や殺菌などの衛生基準を定めました。しかし、南九州独自の鶏肉の生食には基準が設けられなかったため、県は2000年に独自に基準を作りました。
包丁やまな板は83℃以上のお湯で殺菌し専用のものを使うことや食中毒を防止するため、解体方法や肉表面の殺菌、温度管理などを定めています。

(県生活衛生課 下島浩幸食品衛生専門監 ※取材時)「食文化である、生食用食鳥肉その安全を確保するためにはガイドラインをよく周知するということと、それに基づく指導を継続していくということが必要と考えています。」
ただ、食中毒には細心の注意が必要です。
こちらは全国で起きたカンピロバクターという菌による食中毒の発生件数です。

鶏肉以外のものも含まれますが、年間300件あまりで推移しています。
全国では、半生や加熱が不十分な鶏肉料理で、カンピロバクターによる食中毒が多発していて、飲食店で本来「加熱用」の鶏肉を生で提供したケースもあったといいます。
県内では、この5年間にカンピロバクターの食中毒が13件発生し、鳥刺しが原因だったものも1件ありました。
こうしたことから、鳥刺しの安全性を更に高めようと、民間で飲食店や加工業者向けの資格が作られました。それが「鳥刺しマイスター」です。