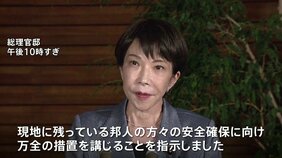災害時に自分たちが住む町を離れて避難する「広域避難」を知っていますか?この広域避難の課題をキャンプを通じて見つけようと、高知市の自主防災組織が仁淀川町で初めて行った防災キャンプを取材しました。
高知市の下知コミュニティセンターに集まった人たち。高知市・二葉町の自主防災組織が初めて開催する「防災キャンプ」の参加メンバーです。参加者およそ30人は仁淀川町の避難所で宿泊を体験します。

(二葉町自主防災会 西村健一 会長)
「泊まってみてどういうところに改善点があるのかとか、何をすればいいのかとか。決まってると思うけど本当にそれができるのかというのがわからないので、それに対して自分らなりの提案ができればいいなと思います」
なぜ高知市民が仁淀川町で「防災キャンプ」をするのか、その理由は「広域避難」です。広域避難とは災害により被災した人が他の市町村へ避難することで、高知市と仁淀川町は2022年に地震発生時の広域避難所に関する協定を締結しています。高知市では、南海トラフ地震発生時最大で4万人分の避難所が不足すると見込まれていて、協定により仁淀川町の2施設が不足分の一部を担うことになっています。これを受け自主防災組織が初めて企画した防災キャンプ。一部のメンバーは実際に広域避難をする時に使用することになるバスで仁淀川町を目指しました。

参加者たちが今回宿泊したのは仁淀川町大植にある「泉川多目的集会施設」で、収容人数はおよそ80人です。

施設に到着した参加者たちは早速、寝床の準備に取り掛かりました。こちらでは折り畳みベッドの上にテントを乗せています。

こうすることで、床や地面が冷たい時や濡れている時でも快適に過ごせるということです。
(参加者)
「広い、横になって完璧にいい感じでいけます。完全にプライバシーが保てるのでちょっと脱いで寝ても大丈夫」
防災キャンプには高知市の職員も参加していて、広域避難への受け止めなどについて官民の垣根を超えたざっくばらんな話し合いも行われました。

参加者からは「思っていたより来やすかった」といった前向きな意見や、「地震の際、高知市から仁淀川町にたどり着けるのか心配」など不安を訴える声も聞かれました。
防災キャンプのもう一つの狙いは「地元の人との交流」。顔の見える関係が避難先の地域との信頼関係をより深めます。高知市と仁淀川町はおよそ50キロ離れていて車で1時間以上かかり、決して近いとは言えませんが、キャンプを通じて心の距離は近づいた様子でした。
(参加者)
「自然が多くて空気もおいしいし楽しいです。(Q・ここで寝泊りできそうですか?)いけそうです」
「1つの選択肢として模擬的に経験しておこうと思い参加しました。今、町の中で暮らしているわけですから、町と同じようにはいかないと思うんですけど、そこはちょっと想定がむずかしいところですよね、どういうことが起こるのか」
そして、防災キャンプの振り返りとして3日、反省会が開かれました。挙げられた課題は「避難先の地域の方々の負担をいかに軽減できるか」や「若い人がもっと参加しないと次の世代に繋がらない」など様々です。
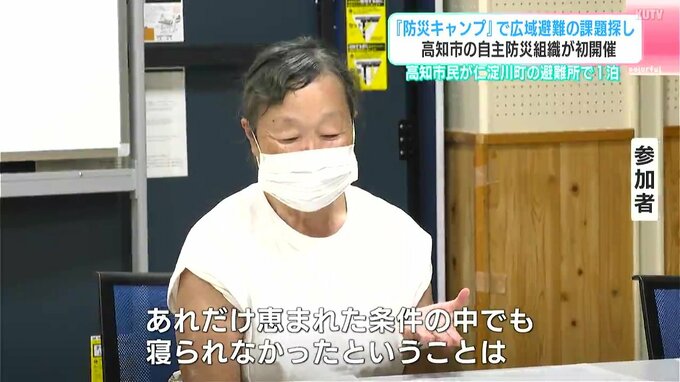
(参加者)
「あれだけ恵まれた条件の中でも寝られなかったということは、避難所へ避難するときは、それはそれは大変だろうなというのが体験して分かった」
自分たちが普段暮らす町を離れて見ず知らずの町に移る「広域避難」。避難の基準や避難所の運営方法、実際に被災した時の心理的ストレスの影響などまだまだ課題は残っていますが、防災キャンプを主催した西村会長は地域間の事前の交流が最も重要だと語ります。
(二葉町自主防災会 西村健一 会長)
「全く知らない土地に避難する、全く知らない人たちが地域にやって来るという不安はものすごいものがあると思うので、仁淀川町だけじゃなくてほかの山間部の地域と連携・交流する、しかも顔の見える交流を事前にやっていくことが一番大事なことやないかと思っています」