世界遺産「知床」。人々の心を魅了する、この海で事故は起こりました。
去年4月23日午前10時、乗客乗員26人を乗せ観光船「KAZUⅠ」はウトロ漁港を出発しました。
知床岬を回る3時間のコース。しかし…。
「船首が浸水して船が沈みかかっている」
午後1時21分。乗客が親族にかけたこの電話が、「KAZUⅠ」からの最後の連絡になりました。
6日後。「KAZUⅠ」は、水深およそ120メートルの海底で発見。
乗客乗員20人が亡くなり、今も6人の行方がわかっていません。
国の運輸安全委員会は事故から1年4か月あまりたった7日、270ページにわたる最終調査報告書を公表しました。
なぜ、船は沈んだのか。
1.ハッチのふたの不具合
7日、初めて公開された事故8日前のハッチの写真です。
ふたと船体に付いている南京錠などを通す穴が揃っていないことから、ふたがおよそ2センチ浮いた状態でした。
高波で船体が揺れてハッチが開き、海水が流れ込んで船が沈没したとしています。
2.運航会社の安全管理体制
「知床遊覧船」の豊田徳幸船長(当時54)は、当日、悪天候が予想されていたにもかかわらず出航。
海に出たあとも引き返したり、避難したりしなかったことが事故の一因とされました。
同業他社の社員は調査に対し、豊田船長についてこう証言しています。
同業他社
「天候判断、海域や地形の把握などの理解度が不足していると感じた」
さらに、事故の背景として「知床遊覧船」の桂田精一社長(60)が安全管理の責任者でありながら、「船に関する知識や経験がなく、その影響は重大」と指摘しました。
3.国の監査・検査の実効性
国が行う検査の実効性に問題があったことも指摘されました。
国の代行機関であるJCI=日本小型船舶検査機構が事故の3日前の検査でハッチのふたを確認したものの、目視のみで「良好な状態」であると判断していました。
乗客家族
「行方不明なので、時間がとまったままになってしまいます」
男性の7歳の息子とその母親の2人は「KAZUⅠ」に乗り、今も行方が分かっていません。
十勝地方に住む父親は公表された報告書をこう受け止めました。
乗客家族
「本当に防げた事故だったのに、検査も監査も全く機能していなかったことと桂田社長のような安全管理を軽視している、自分の利益しか考えていないような会社だったことに憤りを感じます」
報告書をまとめた国の運輸安全委員会は、今回の事故について「過ちの連鎖」だったと指摘しています。
いったいどういうことなのか?
事故の直接的な原因は…。
最終報告書の「結論」
①ハッチのふたの不具合。甲板のハッチが完全に閉まらない状態で出航、高い波によって船が上下したことでハッチが開き、そこから船首に海水が流れ込み、浮力を失って沈没しました。
②「出航した船長の判断」や「運航会社の安全管理体制」に問題があったとも指摘されています。
③「国の監査や検査の実効性に問題」があったことも指摘されています。
事故のわずか3日前、国の代行機関であるJCI=日本小型船舶検査機構の検査で、「ハッチのふた」について「外観から良好」とされ、不具合を見つけられませんでした。
ずさんな会社の体制を、国の検査で改善させることができなかったということが、最終報告書でも示されました。
7日、公表された最終報告書について、水難学会の斎藤秀俊理事に伺いました。
水難学会 斎藤秀俊理事
「第1印象としては、比較的わかりやすい報告書だった。事実は誰も見てないというか、見てた人がいたかもしれないけれども、亡くなられる、あるいは行方不明になってわからない。船の事故(調査)で一番難しいところです」
複数指摘された原因の中で、斎藤理事は、天候が悪化するなか出航に踏み切った判断が一番の原因だと指摘します。
水難学会 斎藤秀俊理事
「報告書で一番は、出航前の天気予報のチェック。出航前にすでに波浪注意報とか気象庁から情報が出ています。これを見て出航中止を、操船者ばかりでなく、運航管理者もみてほしかったというところです」
今回公表された事故原因について、運航会社「知床遊覧船」の桂田精一社長は7日、HBCの取材に対し、「最終報告書をまだ読んでいないが、結論ありきで、こちらの意見が全く反映されていないと聞いている。本当にハッチから水が入ったのかは疑わしい」と答えました。
海上保安庁は、運航会社「知床遊覧船」の桂田社長を業務上過失致死の疑いで立件する方針で捜査を続けています。
全国のトップニュース
【速報】中国が日本産水産物の輸入を再び停止 高市総理の発言への対抗か

大分市佐賀関で大規模火災 焼け跡から1人の遺体みつかる

中国が水産物輸入停止を伝達「ビクビクしながら…」北海道の水産業者からは落胆の声 約2年ぶりに中国への出荷が再開されたばかり

日中問題「長期化のおそれ」局長級協議“平行線”辿る 協議後の撮影で中国側に申し入れ 高市総理の台湾有事巡る発言で

児童手当2万円上乗せへ 経済対策に盛り込む方針 自民党・小林政調会長が明らかに 所得制限設けない方針 必要金額4000億円程度の見通し
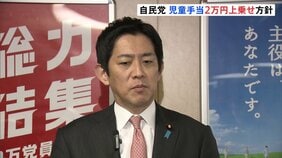
【独自】一部始終がわかる記録入手 建物の隙間で2時間半前から機会をうかがったか 赤坂ライブハウス前女性刺傷 計画的犯行で女性襲撃か
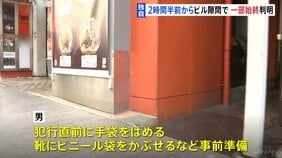
神戸・6歳児を虐待死させ遺棄した罪 母親ら3姉妹の初公判 母親は起訴内容を認める

広島 養殖カキ大量死 鈴木農水大臣が現地視察 高水温・高塩分でカキが生理障害か

