44人が犠牲になった胆振東部地震から、9月6日で5年。
「あの日、何があったのか」を詳しく知ることで、「必ずやってくる」といわれる巨大地震から、命を守るための道すじを見つけていきます。
北海道内を流れる電気の周波数は、本来「50ヘルツ」に保たなければなりませんが、あの日は、需要と供給を一致させることができず、ついに、国内初のブラックアウトに陥りました。
地震発生からの「17分間」、一体、何があったのでしょうか。
震源は胆振地方中東部。取材で安平町にいた記者は…
佐伯裕斗記者
「本棚が崩れています。電気もつきません」
震源から20キロの位置にある「北海道電力 苫東厚真発電所」。
地震によって、3基ある発電機のうち、2号機と4号機が自動停止。
地震の18秒後、発電が止まりました。
ここは、北海道内最大の火力発電所で、当時、道内の電力のおよそ半分の発電を担っていました。
電力が減った瞬間、道内各地の発電所や変電所で、強制的に停電させるシステムが作動。
電力不足を意味する=周波数が大きく落ち込んだのです。
北見工業大学電力工学研究室 小原伸哉教授
「北海道は50ヘルツの周波数の電力ですが、(電力会社は)逸脱すると電気を止める。止めないと、あちこちで事故が起きたり、いろんな異常動作が起きるということがあります」
北海道の電力事情を研究する北見工業大学の小原 伸哉教授の監修のもと、小学生向けの模型で実験しました。
5つの豆電球は、電力を使う私たちの住宅や工場、コンビニなど。
そして、記者が持っている「手回し発電機」が発電所です。
松本雅裕記者
「結構頑張ってますけど、疲れて回転が遅くなると落ちますね」
北見工業大学電力工学研究室 小原伸哉教授
「回転のスピード、これが電気の周波数になります。たくさん回すと周波数がたくさん山が流れて、ゆっくりすると山がゆっくり流れて供給量が減る」
手で回す発電機のスピードが一定でない、つまり、周波数が乱れると、電気製品が正しく動かなかったり、火が出たりして事故が起こる可能性があるため、一部の地域を停電させる必要があるのです。
さらに、震源に近い厚真町でも…。
松本雅裕記者
「震度7の揺れが襲った厚真町では、あちらの送電線の電線が大きく揺れて鉄塔に接触、ショート事故が起きました」
道央と道東を結ぶ主力の送電線「狩勝幹線」で地震によるショートが原因で、電気が流れなくなってしまったのです。
電力を失った道東の複数の水力発電所もストップ。
道内は「ブラックアウト」寸前まで追い込まれました。
この時、危機を救ったのは、本州からの緊急送電でした。
電力不足は一旦、回復したかのように見えました。 ところが…
【午前3時11分 地震から4分】
地震に驚いた人たちが、次々に照明やテレビをつけるなどして電力の需要が一気に増えたため、電力が不足し、周波数が落ちていったのです。
竹馬悠記者
「歩行者の方々が状況を確かめている状態です」
【午前3時21分 地震から14分】
再び、苫東厚真発電所です。
唯一発電を続けていた1号機に負担が集中、ボイラーが限界に達していたのです。
【午前3時25分 地震から17分】
午前3時25分、1号機は「停止」しました。
これをきっかけに、道内の他の発電所もドミノ倒しのように発電がストップ。
北海道から電源が失われた瞬間でした。
さらに、最後の砦だった、本州からの電気も受け取れなくなり、道内295万戸が停電。
国内初のブラックアウトに至ったのです。
北見工業大学電力工学研究室 小原伸哉教授
「当時バックアップや大きな発電所が落ちたときに、どうやって電力を回復するか、そういったものが足りなかったというところだと思います」
【午前4時00分 ブラックアウトから35分】
北電は「ブラックアウト」からの復旧 「ブラックスタート」に動きます。
最優先で電気を送らなくてはならない場所があったのです。
それは、泊原子力発電所です。
使用済み核燃料の冷却水を循環させるポンプなどは「電気」で動きます。
東日本大震災で、東京電力福島第一原発では、外部の電源を喪失。
核燃料を冷却できず「メルトダウン」。
建屋が爆発したのは、記憶に新しいところです。
【午前6時30分 ブラックアウトから3時間5分】
ブラックスタートで重要な役割を果たした発電所は、日高山脈の山中にあります。
新冠発電所です。
放水を始めて、発電が始まったのは午前6時30分すぎ。
ログには「1.0」1000キロワットと記録されていました。
水の力で電気を作る水力発電所は、種火のような「非常用発電機」の電気でも動かすことができるからです。
長引く停電の影響が、道内に広がり始めます。
買い物客
「揺れた瞬間は電気が点いていたんですよ。大丈夫だと思って寝て起きたら停電していて。(住宅が)すべて電気で、お湯を沸かせない」
多くの道民が、電力の早い復旧を求めていましたが、作業は慎重に、慎重に、進められました。
北見工業大学電力工学研究室 小原伸哉教授
「電力の需給バランスを見て、電力がどれくらいの量が必要か、どこの発電所を、どのようなルートで電気を送らなくてはいけないか、一番早く解決するかということを全部計算している。これを一つ一つ慎重にやっていかないとまた(電力が)落ちてしまう」
しかし…
【午前9時18分 ブラックアウトから5時間53分】
北電・苫東厚真発電所から消防への通報音声
「北海道電力の苫東厚真発電所ですけれども(何が燃えています?)タービン設備のところから火が出ている、今、消火活動中です」
苫東厚真発電所4号機のタービンが出火。
道内最大の発電能力を誇る「復旧の切り札」を失ったのです。
北電 真弓明彦社長(当時)
「3台の復旧には少なくとも1週間以上かかる見通し。すべての電源が落ちてしまうということ、苫東の3台のみならず、そこのところのリスクは低いとみていました」
北電は、苫東厚真以外の火力発電所を1か所ずつ再稼働させて、停電は徐々に復旧。
さらに本州からの送電も再開され、地震から3日目=8日午前0時13分、ようやく道内のほぼ全域で停電が解消されました。
北電はブラックアウトの教訓から、以下のような再発防止対策を進めています。
・本州との電力をやり取りするルートを増強。
⇒5年後には電力量は倍になる予定です。
・送電線の揺れの防止と鉄塔の基礎の補強
・石狩湾新港LNG発電所の発電機 増設予定。
⇒発電所の分散で一極集中を回避したいが、まだ先。
全国のトップニュース
【速報】中国が日本産水産物の輸入を再び停止 高市総理の発言への対抗か

大分市佐賀関で大規模火災 焼け跡から1人の遺体みつかる

日中問題「長期化のおそれ」局長級協議“平行線”辿る 協議後の撮影で中国側に申し入れ 高市総理の台湾有事巡る発言で

児童手当2万円上乗せへ 経済対策に盛り込む方針 自民党・小林政調会長が明らかに 所得制限設けない方針 必要金額4000億円程度の見通し
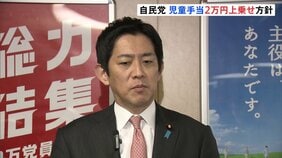
【独自】一部始終がわかる記録入手 建物の隙間で2時間半前から機会をうかがったか 赤坂ライブハウス前女性刺傷 計画的犯行で女性襲撃か
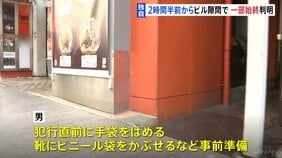
神戸・6歳児を虐待死させ遺棄した罪 母親ら3姉妹の初公判 母親は起訴内容を認める

「シャインマスカット」の苗を無許可販売か 54歳女性を書類送検「売ればお金になりコンビニでお菓子を買った」 警視庁 海外に流出していないかなど調べる方針

広島 養殖カキ大量死 鈴木農水大臣が現地視察 高水温・高塩分でカキが生理障害か

