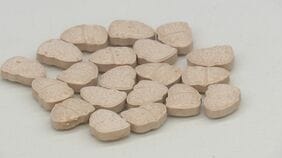これは「鎮圧」と呼ばれるリンクを作る前の作業。
霜柱などで、デコボコになったグラウンドをならし、滑らかなリンクを作るための、大切な準備です。
運転しているのは、斎藤一成さんら、PTAのメンバー。
斎藤さんたちは、ここ大正小学校の卒業生で、今は農業を行っています。
だから、こんな重機を扱うことができるのです。

斎藤さんは「冬休みや土日に、ちょっと学校に来て、すぐ滑れるような環境を整えてあげられる限りは続けていければなと思いますね」と話します。
ほかのPTA役員も、「綺麗なピカピカなリンクを作りたいです今年も。鏡のような」と意気込みます。
鎮圧作業は雪が降るまで続けられ、雪が校庭を覆う頃になると…

再びグラウンドには重機の姿がありました。
今度は「雪ふみ」という作業です。
雪ふみというのは、雪を踏み固め、水の受け皿を作るための作業のこと。
これを行わないと、グラウンドに水をまいても地面に染み込んでしまい、きれいなリンクが作れないのです。

これで完成…ではありません。
PTA会長は「まだ今日の雪が足りないので、また明日雪が降る予報なので、その後も踏み固めて下地ができるかなっていう感じですね」といいます。
雪ふみの目安は、厚さ10㎝くらい。
やっと水を撒く下地が完成です。

PTAの皆さんが、ここまで3週間ほど作業を続け、ようやく「水をまく」ところまでたどり着きました。
ここからリンクを作るには、さらに400トンの水を数回に分けてまかないと完成しないのです。

ちなみに400トンの水は、一般的な学校のプール1杯分に相当します。
これは、1月4日現在のグラウンド。
年末から水まきを始め、この日までに180トンほどの水がまかれた状態です。

一見完成したように見えますが、凹凸のないリンクにするには、最後の仕上げが必要。
深夜1時近くになると、まいた水もたちまち凍る気温マイナス20℃。
鎮圧作業から33日、ようやく、きれいなスケートリンクが完成しました。

斎藤さんは「いいリンクができていると思う。スケートが好きな子、嫌いな子がいるとは思うんですけど、みんなが経験できるのは小中学生のうちだけなんで。うまい下手関係なくみんな経験してほしいですね」と話していました。