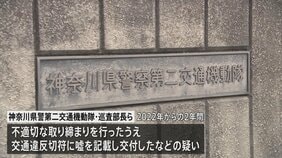食べるしかない“生臭いニシン” 起死回生の一手とは?
しかし、最後まで慣れなかったのがニシン。私は、この話を聞いた時は、そう悪くないメニューとも思ったが、詳しく内容を聞いて食欲は減退した。そのニシンは焼いたものではなく生なのだ。しかも、新鮮とは程遠い、臭いニシン。それを生のままで食べる。毎食、この食中毒リスクとの闘いでもあったが、食べないという選択はあり得なかった。なぜなら、この腐敗し始めているニシンであっても、貴重なタンパク源であり、それは陽が昇り始めたら確実に訪れる重労働の活力源になるからだ。どれだけのニシンを生で食べたであろうか。

「食えたものではなかった」と表現した黒パンと生ニシンがセットだったが、ノルマを満たさないと減らされた。食事の量が減れば、入る力も入らない。そうなると、必然的に仕事の質は下がり、採炭の効率はみるみるうちに落ちていった。

それに追い打ちをかけるような厳しい寒さも続いた。マイナス30度から40度の極寒のシベリアで凍傷になったり、体力が尽きて倒れたりする人も絶えなかった。「このままでは、こっちが参ってしまう。死ぬかもしれない」。追い込まれた彼は、ここであることを思いついた。それは、人生を大きく変えるきっかけでもあり、好奇心旺盛で、なんでもトライしてみようというバイタリティー豊富な彼だからこそなし得た起死回生の策だった。
「そうだ、ロシア語を覚えよう!」
この思いつきが、その後の抑留生活を劇的に変え、ターニャと出会うことになるとは知るはずもなかった。
【関連記事】
・80年間封印されたロシア人女性との“禁断の恋” 命つないだロシア語への執念②
・強制労働先で出会ったロシア人女性「瞳は丸く大きかった」③
・忘れられないターニャの「ボルシチ」④
・ 「ハルオ、私と一緒になって」 知る由もない祖国の状況・未練⑤
CBCテレビ 解説委員 大石邦彦