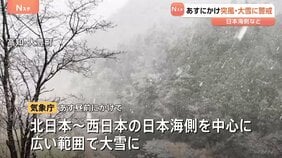馬に乗りながら、手を伸ばしたり、横座りしたり…、馬の背中で様々な姿勢をとる女性。これはスポーツではなく、「ホースセラピー」と呼ばれるリハビリの一種です。揺れる馬の背中で体幹やバランス感覚を養う効果が期待され、何より生きている馬との交流そのものが癒しにつながっています。ホースセラピーを受けている家族と、実施する牧場を取材しました。
「子どもを馬に乗せたい」という要望から始まったホースセラピー

愛知県豊橋市の緑豊かな場所にある「ピッコロファーム」。長江清仁さん・久美子さん夫妻が経営するこの小さな牧場には、ヤギ3頭に犬が2匹、そして馬7頭が暮らしています。
ホースセラピーを始めたのは12年前。きっかけは脳性麻痺の双子を持つ保護者から寄せられた「子どもを馬に乗せたい」という要望でした。
(ピッコロファーム・長江清仁さん)
「馬を使って何かできないかなと思っていた。乗馬だけではなくて。(障害のある子どもの)親の願いというか、少しでも子どもにプラスなことはないかという願いがあって、それに引っ張られた」
サラブレッドやポニーなど乗馬体験用の様々な馬がいる中、ホースセラピーを担当するのは北海道原産の品種、道産子の「まるちゃん」です。
(ピッコロファーム・長江久美子さん)
「背中が広くて温厚で、おっとりしている馬。(Q背中が広いのは重要?)そうですね、横を向いたりとか寝かせてあげたりとかするので」
重い荷物を運ぶのに使われてきた道産子は、体高が低く、頑丈なのが特徴。性格は温厚で、ホースセラピーに適しています。
温厚な性格の道産子「まるちゃん」も入念に準備!

ホースセラピーの利用予定が入っている日は、予約時間の約30分前から馬のまるちゃんの準備が始まります。
(ピッコロファーム・長江久美子さん)
「馬房はやはり狭い。馬の体をほぐしてあげて、馬の脚の歩様に問題がないのかチェックもするし、主人が馬をコントロールしているが、きちんと音声に反応するのか、安全に乗せられるかというチェックもしている。いきなり馬房から出して馬具を付けて、ポッと乗るということは絶対にしない」
道産子がいくら温厚でも、雑に扱うと乗る人を受け入れない恐れもあるため、まずは落ち着かせてゆっくり準備します。
セラピーを受けるのは、小林咲貴さん(12歳)。脳性麻痺で歩くことができず、普段は車いすに乗っていますが、ホースセラピーは3歳から9年間続けています。馬に乗るときはスロープを使って馬のそばまで近づき、支えられながら背中にまたがります。
ゆったりとした揺れにバランスをとりながら、馬とともに前に進む咲貴さん。しばらく歩いた後、咲貴さんのお父さんが取り出したのは太鼓ゲームのバチ。咲貴さんお気に入りの太鼓バチを持たせたことで、持ち手から両手を離し今度は体幹だけでバランスを取りながら歩きます。