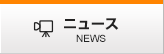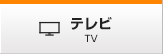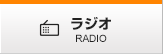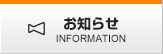異例の早さとなった梅雨明けの発表、一体、なぜなのでしょうか。
そして、これにより今後注意すべき点を専門家に聞きました。
気象台は28日、「中国地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。
これまでの記録より5日早く、最も早い梅雨明けで、期間も14日間と、これまでの記録より8日短く、最も短い梅雨となりました。
なぜこんなに早い梅雨明けとなったのか?専門家に聞きました。
元高松地方気象台広域防災管理官 近藤豊さん
「この赤いラインが平年の太平洋高気圧の位置です。通常この時期だと、まだ日本の南海上までしか覆っていない。ところが、今年はもう日本付近を広く太平洋高気圧が覆ってしまった。それに合わせて、梅雨前線帯に沿うように流れる偏西風も、太平洋高気圧が北上したことによって、日本の北まで持ち上げられました。要するに、梅雨前線も一緒に北上してしまった」
それでは、なぜ太平洋高気圧は北上したのでしょうか。
元高松地方気象台広域防災管理官 近藤豊さん
「今年は、ラニーニャ現象がまだ続いていると言われている。ラニーニャ現象とは、フィリピンの東海上で熱帯の暖かい空気がどんどんたまり、大きな低気圧を作る。その低気圧を補うために、お隣にある高気圧やインド洋の高気圧がどんどん勢力を増して、北へ北へ北上した」
また、専門家は、今後の雨の降り方について2つのポイントを指摘します。
元高松地方気象台広域防災管理官 近藤豊さん
「1つは、梅雨が明けたからといって、全く雨が降らないわけではない。夏の時期、夕立、不安定な降水、これは間違いなく起こってきます。また、前線も北上したといっても、南下しないとも限りません。」
そして、もう1つのポイントは、「年間降水量」です。
元高松地方気象台広域防災管理官 近藤豊さん
「今回梅雨期間に雨が降らなかったということは、どこかで必ず補ってくるわけです。例えば、秋雨台風で補う、短時間による集中豪雨、いわゆるゲリラ豪雨」
引き続き、雨の降り方には十分に注意してほしいとしています。
全国のトップニュース
【解説】捜査前進の陰に「トクリュウの弱点」 闇バイト強盗・指示役逮捕 幹部が明かすウラ側 携帯など約750台解析

【速報】自民・維新が議員定数削減法案を国会に提出

旧統一教会・田中富広会長が辞任へ 高額献金「補償委員会」設置など区切りに 今後、記者会見し表明予定 高額献金被害の元信者らへの謝罪表明も検討

【速報】高市内閣 閣僚の平均資産は約6641万円 トップは小泉防衛大臣で2億7248万円

勾留中の被告(54)が7階窓から逃走…逃げた状況が明らかに その後、静岡・三島市内で確保 伊豆の国市の病院で警察官監視のなか

【速報】コメ平均価格5キロ4335円 過去最高値を更新

中国「過去最大規模」100隻超の艦船を東アジアに展開 高市総理の発言に反発か 軍事演習など動向注目

埼玉・朝霞市放火殺人で「懲役29年」判決 元内装業の男(40)に 頭をバールで複数回殴り火を放ち殺害「無残な最期 苦しみは想像絶する」さいたま地裁

カテゴリ
Copyright(C)1997 BSS INC.