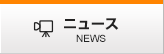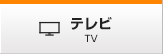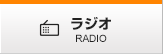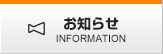地域によって「大きな差」が出るワケは?
日本民謡の変遷をデータ分析している同志社大学の河瀬彰宏准教授に話を聞きました。
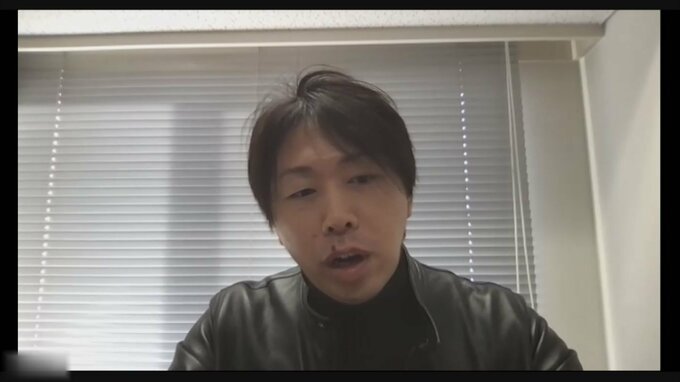
同志社大学文化情報学部 河瀬彰宏 准教授
「率直な感想としては、地域性があふれる歌詞が使われているところです。具体的には、ゲゲゲの鬼太郎とか、ぎっこんばっこん、これも割と様々な地域で見かける機会はあるんですけど、古今和歌集でも船の歌が山陰地方でよく出てきますので、船に関わるような、上下に動いたりっていう動作を伴うような単語があるなと」
このわらべ歌が見つかったのは、100年以上前の1911年頃だといいます。
そして、様々な種類がある背景には、基本のリズムに合う歌詞を、子どもたち自身が作り出していることが考えられると河瀬准教授は指摘します。
同志社大学文化情報学部 河瀬彰宏 准教授
「子どもの歌なので、遊びの中で何か目的があって使われる歌ですから、動作が伴う音楽になっている。基本的には、動作にはリズムが関係してくるんですけど、基本のリズムがあって、そこに地域とか郷土性のある単語が当てはめられていくという流れがあると思います」
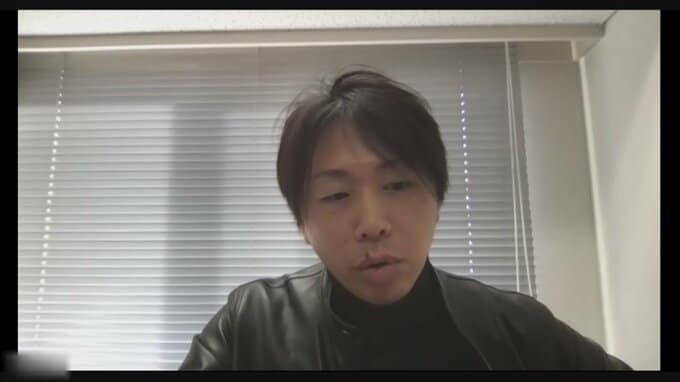
つまり、基本となるわらべ歌があって、そこに地域の子どもたちが、その場所・時代にちなんだ言葉を言わば好き勝手に紡いでいきます。
そのため、小さなコミュニティーごとに、全く違う多くの種類のフレーズが誕生したと考えられるというわけです。
そして、子どもが考えているからこそ、意味で捉えようとすると、規則性が見つけにくいのだと言います。
同志社大学文化情報学部 河瀬彰宏 准教授
「昔、柳田國男先生や北原白秋先生が、こういったわらべ歌を、歌詞に基づいて分類しようと思ったんです。ただ、それがどうもうまくいかないというのが、子どもの歌なので、遊びの中で何か目的があって使われる歌とあって、動作が伴う音楽になっているんです。基本的には、動作にはリズムが関係してくるんですけど、基本のリズムがあって、そこに地域とか郷土性のある単語が当てはめられていくという流れがあると思います」

「どれにしようかな」は、わらべ歌の中の「となえうた」に分類されるとのこと。「となえうた」の目的は、人や物を候補の中から選ぶことであるため、原則として1文字ごと、1拍ごとに指を指していく動作が伴います。
最後に指したものが気に入らないものだったり、自分の希望にそわないものが出てきた場合には、子どもたちは即興的に歌詞を繋いでいくことがあり、その即興的に出てくる歌詞には、子どもたちが日頃見聞きしているものが入ってくるのだそうです。