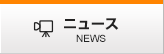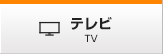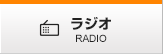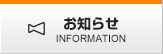この日、向かったのは島根県安来市の荒島墳墓群にある塩津山1号墳です。
山陰道のトンネルの上に保存された墳丘は築造当時の姿が復元されています。
ピラミッド形の「方墳」に分類されている古墳ですが、近寄って見ると。
島根大学・岩本崇准教授
「側辺がですね、カーブして来てこの角が少し張り出すような形になっています。古墳時代の最初期のもので、四隅突出型墳丘墓の最後のやつなんだという風に、最後の四隅なんだという風に言われていたんですけども、一方で出て来る土器は新しい。四隅突出型墳丘墓に似せた方墳であるという風な言い方が出来ると。」
この古墳を築いたのは、中央の倭王権と関係が深い新しい勢力と考えられています。
その時、古墳の形を以前の四隅突出型墳丘墓に似せたのは、地域固有のやり方に配慮して葬送儀礼の「復古再生」が図られたのだろうというのです。
「国譲り神話」では出雲は力ずくで脅されて高天原に服従したことになっていますが、「復古再生」が必要だった背景として、事実は強権的併合ではなく連合といったもので、倭王権自体も出雲と対立する存在ではなかった可能性すら考えられるようです。
島根大学・岩本崇准教授
「想像でいくとですけども、そういう(弥生時代の出雲の)人たちが倭王権の基盤になってるっていうことはあり得る。近畿の王権が成立する(奈良県)桜井のエリアですね、あの辺って出雲系の土器結構出る。」