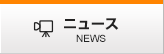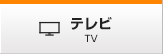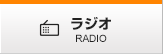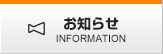国内で発掘された三角縁神獣鏡は約580枚で、卑弥呼が中国の魏王朝からもらった「銅鏡百枚」なら数が多過ぎることや、元の中国では鋳型を含め1枚も発見されていないなどいくつもの謎があります。
島根大学・岩本崇准教授
「日本で出ているの(銅鏡全部)が6000枚位なので、そのうちの多分まあ4000位はやってる(実測済み)のかなと。自分で図、書いたのは覚えてますんで。」
岩本准教授は1枚1枚断面図を作成。
手書きファイルとして年代ごとに整理する中で、断面の形と模様が互いに関連していて、造られた時期を絞り込めることに気付いたといいます。
島根大学・岩本崇准教授
「模様の類似性が低い場合、相違点が大きい場合は鏡の形も変わっているということが分かりましたので、そこを追究していった。注目されていない鏡の断面形態から、三角縁神獣鏡分類するっていうことは、先行研究を読むだけでも(未解明な点の)その道筋は得られた。」
古墳時代前期から中期初めにかけての年代の指標となることを明らかにした岩本准教授。
それによって古代出雲についての考察も深まって来ています。