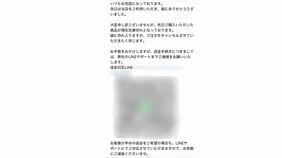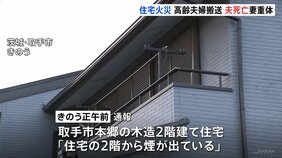なぜ、青森県・大間漁協のマグロ漁船が転覆したのか。その分析で専門家が注目しているのは、「大間埼灯台周辺の海域」です。船の位置が、最後に確認できた場所であると同時に、「急に風や波が変わることが起こりやすい場所」だといいます。
※水難学会 斎藤秀俊 理事
「波が高いとか低いとかの問題ばかりでなく、急に風の様子が変わるとか波の様子が変わるとか、こういった所は事故が起こりやすい」
水難事故を防ぐための研究に取り組む「一般社団法人 水難学会」の斎藤秀俊理事です。斎藤理事が注目しているのは、19日午後6時43分、「第二十八光明丸」の位置が最後に確認できた場所「大間埼灯台から北に約1キロ付近の海域」です。
※水難学会 斎藤秀俊 理事
「(漁場と漁港を)行き来するときに岬の山が背になるか、背に何もなくなるかで大きく変わる。(19日の最終確認位置は)急に風が変わったとか波が変わったとかいうことが起こりやすい場所」
この海域は、地元の漁師も「潮の流れに特徴があり注意が必要だ」といいます。
※地元・大間の漁師
「潮の流れが速いから、あそこは気をつけなければ」
また、斎藤理事は、捜索は時間との勝負だと強調します。19日の夕方の現場の海水温は11℃で例年より高く、しばらくは泳ぐことができるものの、数時間後には命の危険が出てくるといいます。
※水難学会 斎藤秀俊 理事
「体温が下がるのは数十分。意識がなくなるなど、いろんな症状が出てくるのは数時間」
斎藤理事は、藤枝さんの発見を急ぐとともに、漁業に従事する人の命を守るためにも転覆事故の原因究明が急務だと訴えています。